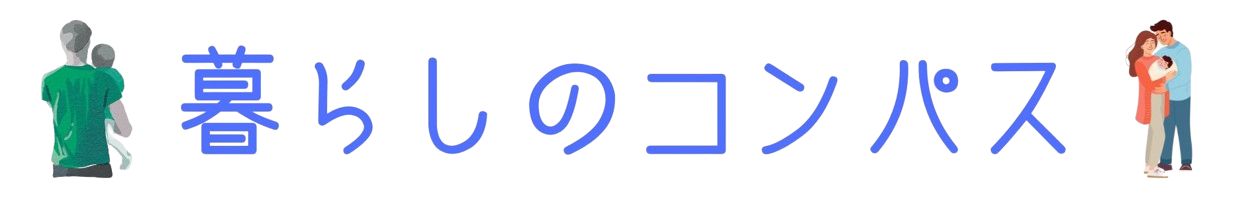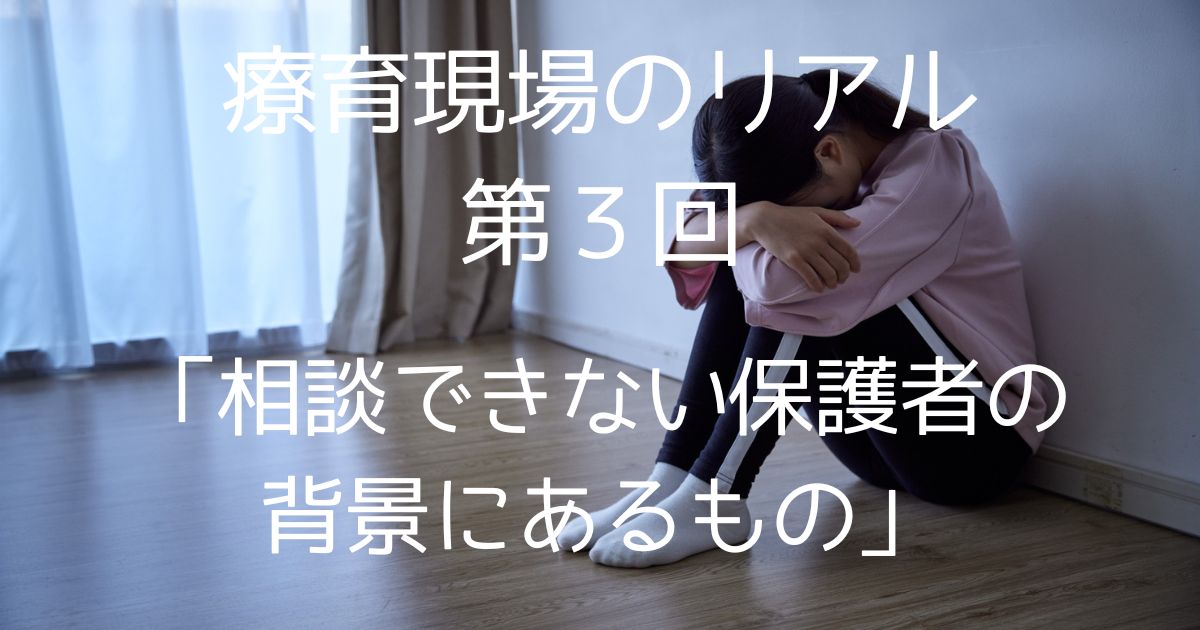こんにちは、社会福祉士のまっさんです。
前回は、「子ども中心支援の落とし穴」として、保護者が抱える“見えにくいしんどさ”に焦点を当てました。今回はさらに掘り下げて、「相談したくてもできない保護者」の心の奥にあるものを、社会福祉士の視点から紐解いていきます。
「困っているはずなのに、相談してこない」その理由とは?
療育現場や福祉の現場では、「支援が必要なのに、なぜ相談してこないのか」という場面にたびたび出会います。
- 書類を出してくれない
- 面談に応じない
- 支援の説明に対して、反応が薄い
- 急に連絡が取れなくなる
こうした保護者を「非協力的」と判断してしまうケースもありますが、それはとても表面的な見方です。
実際には、“相談できない理由”が、ちゃんと存在しています。
保護者の背景にある「相談へのハードル」
保護者が支援を避けてしまう背景には、さまざまな理由があります。ここでは、現場でよく見られる4つのパターンを紹介します。
1. 【過去の経験】相談しても変わらなかった、むしろ傷ついた
「何度も相談したけど、話をちゃんと聞いてもらえなかった」
「『もっと頑張ってください』と言われて終わった」
そうした**“失望体験”**は、心に深い傷を残します。
結果、「また否定されるかもしれない」という思いから、相談そのものを避けるようになるのです。
2. 【自己責任感】親として頑張らなきゃという思い込み
「こんなことで頼ってはいけない」
「うちだけが大変なんじゃない」
「親としてもっとしっかりしなきゃ」
こうした“親としての責任感”は美徳でもありますが、過剰になると支援を受けること自体に罪悪感を感じてしまいます。
3. 【情報過多】どこに何を相談すればいいか分からない
発達支援の制度や窓口は増えつつありますが、そのぶん複雑化もしています。
「療育?保健センター?相談支援?何が違うの?」
情報が多すぎて、結局何をすればいいか分からないという保護者も少なくありません。
4. 【見えない孤独】身近に理解者がいない
最も深刻なのがこのケース。
「誰にも話せない」
「家族にも分かってもらえない」
“わかってもらえない”という孤独は、自己否定や諦めにつながりやすいのです。
社会福祉士にできる“橋渡し”
こうした保護者に対して、社会福祉士としてできること。それは、「相談」へのハードルを下げる工夫をすることです。
相談=特別な行動ではないと伝える
「困っているから相談する」は、当たり前のこと。でも、支援を“お願い”と捉える人は多くいます。
「支援は、権利です」「誰でも使っていいんです」と、肯定的なスタンスで伝えるだけでも受け入れられ方が変わります。
話しやすい場をつくる
面談室でなくてもいい。玄関先、送迎のとき、帰り際の一言…「今日、ちょっと大変そうでしたね」「最近、夜は眠れていますか?」
雑談レベルのやりとりから始めることが信頼につながります。
“評価”ではなく“理解”を意識する
支援者が「親の努力不足」「対応の問題」と感じてしまうと、その空気は伝わります。
親が安心して話せるためには、評価ではなく理解の姿勢が何より大切です。
保護者支援のカギは「共感」と「選択肢」
「支援してあげる」ではなく、「支援を一緒に考える」
その姿勢が、保護者の心の扉を少しずつ開きます。
「あなたの悩みは、あなただけのものじゃない」
「同じように困っている人がたくさんいます」
そう伝えられるだけで、相談へのハードルはぐっと下がるのです。
最後に|“わかってもらえる”体験が、支援の第一歩
子どもの支援は、親の安心から始まります。
「この人なら、わかってくれそう」
そんな直感的な安心感こそが、保護者支援の最大の鍵です。
私たち社会福祉士の仕事は、制度の説明やサービス調整だけではありません。
“誰にも相談できない”という孤独にそっと寄り添い、“また話してもいいかも”と思ってもらえる関係性を築くこと。
それこそが、すべての支援の入り口になるのです。
次回は、「第4回 “普通でいてほしい”気持ちと向き合う|家族の期待と現実のあいだで」
発達に特性のある子どもを育てる中で、多くの家庭が直面する「普通」という言葉の重み。その正体に迫ります。
関連記事はこちら
⇒第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
⇒第2回 困っている親に寄り添うという支援|子ども中心支援の落とし穴