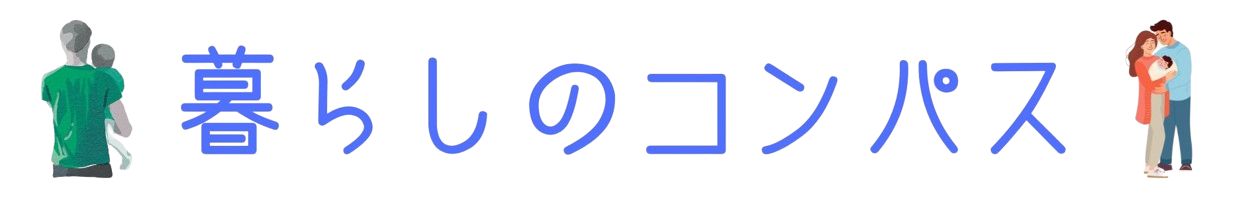「何度トイレに誘っても断られる…」
「周りの子はできているのに、うちの子は全然…」
トイトレが進まないと、不安や焦りで心がいっぱいになりますよね。
私はこれまで、発達に特性のあるお子さんを中心に、200組以上の親子を支援してきました。
本記事では、「トイレに行かない・嫌がる・成功しない」そんなお悩みを乗り越えるための7つのステップをご紹介します。
今、この記事を読んでいるあなたに、少しでも安心と希望が届きますように。
トイトレがうまくいかない原因

1. 体の発達がまだ整っていない
- 膀胱や腸の発達が未熟だと、尿意や便意をしっかり感じ取ることが難しいです。
- 「出る感覚」がつかめないと、タイミングよくトイレに行くのも難しくなります。
- 1〜2時間、おむつが乾いている時間があるか?
- 便秘や下痢が続いていないか?
2. トイレに対する不安・恐怖がある
- トイレが「暗い」「音が大きい」「冷たい」など、感覚的な苦手さから、怖がってしまうことも。
- 特に、感覚過敏がある子は、便座の冷たさや流水音を強く怖がることがあります。
- トイレに入るのを嫌がっていないか?
- 流す音を怖がる様子がないか?
3. 「トイレ=嫌な場所」という印象を持っている
- トイレで失敗して怒られた経験があったり、無理に座らされたりすると、トイレ嫌いになりやすいです。
- トイレの声かけや誘い方が「強制的」になっていないか?
- 失敗時にネガティブな反応をしていないか?
4. 排泄行動に興味がまだ薄い
- 「トイレでおしっこする」ということに、まだ興味が持てない子もいます。
- 排泄がどんな意味を持つのか、体験やイメージが育っていない段階かもしれません。
- トイレの絵本や動画に興味を示しているか?
- 親やきょうだいのトイレ行動に関心を持っているか?
5. タイミングやリズムが合っていない
- 排泄しやすいタイミング(起床後・食後など)に誘えていないと、成功体験がなかなか積めません。
- 毎日同じタイミングでトイレに誘っているか?
- 子どものリズムに合わせた声かけができているか?
6. おむつ・パンツの違いが理解できていない
- おむつとパンツの違い、トイレに行く意味が、まだあまり実感できていないこともあります。
- 「濡れたら気持ち悪い」「トイレに行ったら快適」という感覚を育てることが大切。
- パンツに変えたときに、違和感を伝えてくるか?
- 濡れたことを気にする様子があるか?
7. 発達特性が関係している
- 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)がある場合、こだわりや感覚の違いからトイレトレーニングが難航することも。
- こだわりが強いと「いつもと違う」トイレ行動への抵抗感が出やすいです。
- 環境の変化に敏感だったり、強いこだわりを持っていないか?
- 感覚過敏(音・におい・感触など)が強くないか?
【トイトレ】トイレ自立を促す7つのステップ

ステップ① まず「トイレに興味を持つ」ことから始めよう
トイレ自立の最初の一歩は、「トイレってなんだろう?」という興味を育てること。
特に、トイレを怖がる子どもには、いきなり連れていくだけではうまくいきません。
おすすめは、
- トイレがテーマの絵本やアニメを一緒に楽しむ
- 好きなぬいぐるみと一緒にトイレに行くごっこ遊びをする
- トイレを明るくかわいい空間にする(キャラクターグッズやカラフルな飾りつけ)
「トイレ=楽しい場所」というイメージ作りがとても大切です。
ステップ② 小さな「できた!」をたくさん積み重ねる
トイレに座れたら大成功!
たとえ排泄ができなくても、座るだけでOKと考えましょう。
大切なのは、できたことをしっかり認め、ほめること。
- 「すごいね!トイレに座れたね」
- 「ちゃんとトイレに行けたね」
こうした声かけが、子どもの「またやってみよう」という意欲を育てます。
ごほうびシールやスタンプカードを使うのもモチベーションアップに効果的ですよ。
ステップ③ スモールステップで進める
一気に「トイレでおしっこできるようになろう」とすると、子どもにとってハードルが高すぎることも。
たとえば、
- まずはトイレに入る
- 次はズボンとパンツを自分で下ろす
- 次は便座に座る
- それから排泄にチャレンジ
といった具合に、小さなステップに分けて取り組みましょう。
一つ一つクリアしていくことで、子どもに「できた!」という自信が育ちます。
ステップ④ トイレ環境を子どもに合わせて整える
子どもが安心してトイレを使えるよう、環境を整えることも大切です。
- 子どもサイズの補助便座を使う
- 踏み台を置いて、足がしっかり床につくようにする
- トイレの壁に好きなキャラクターのポスターを貼る
- 明るい照明にする(暗いと怖がる子も多いです)
「自分だけのトイレコーナー」を作ってあげるようなイメージで工夫すると、ぐっと行きやすくなります。
ステップ⑤ 排泄のタイミングを見極める
成功率を上げるためには、排泄しやすいタイミングで誘うことがポイントです。
たとえば、
- 朝起きた直後
- 食事の後
- 入浴前
- 外出前
など、リズムをつかみやすい時間帯に「トイレ行ってみようか?」と声をかけてみましょう。
無理やり誘うのではなく、「今なら行けそうだね」と自然な形で促すことが大事です。
ステップ⑥ 失敗しても責めない
おもらしや失敗は、トイレトレーニングの過程で必ずあるものです。
失敗を責めたり、怒ったりしてしまうと、子どもはトイレに対して「怖い」「嫌な場所」というイメージを持ってしまいます。
失敗しても、
- 「大丈夫だよ」
- 「次はトイレでできるといいね」
と、前向きな声かけを心がけましょう。
大人の心の余裕もとても大切ですね。
ステップ⑦ うまくいかないときは専門家に相談を
トイレトレーニングがなかなか進まない場合、身体的・心理的な要因が隠れていることもあります。
たとえば、
- 感覚過敏(便座の冷たさ、音など)
- 便秘
- 排泄に対する不安が強い
などがあると、トイレに行くこと自体が難しくなります。
そんなときは、小児科医や療育センター、作業療法士(OT)などに相談するのがおすすめです。
一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、子どもに合った支援を考えていきましょう。
まとめ|トイトレは「子どものペース」を大切に

トイレ自立は、単なる生活習慣の獲得ではありません。
子どもにとって「できた!」という達成感や自信を育む、とても大事な経験です。
焦らず、怒らず、楽しみながら。
お子さん一人ひとりのペースに寄り添い、小さな成功を一緒に喜んでいきましょう!
【関連記事もおすすめ】
・自宅療育グッズおすすめ10選|発達障害をサポートする知育玩具