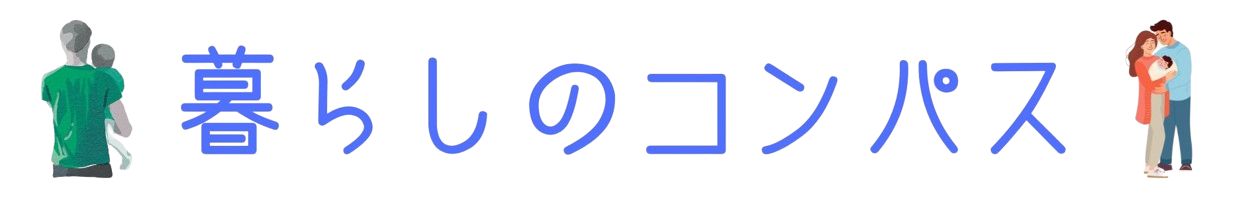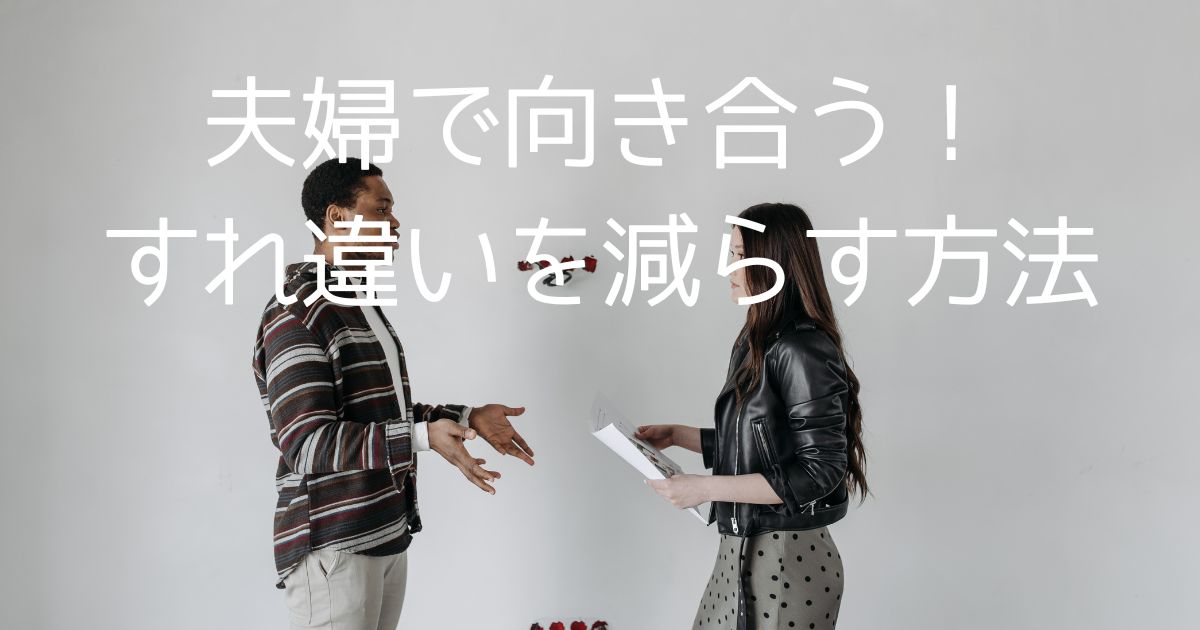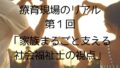発達障害のある子どもの育児は、日常の中にたくさんの工夫と配慮が求められます。
療育の送迎、園や学校との連携、家庭での関わり方――どれも一人で背負うには重すぎるテーマです。
しかし、療育の現場で保護者面談を重ねるなかで、私は何度もこんな言葉に出会ってきました。
「夫が分かってくれない」
「妻と意見が合わず、ケンカが増えた」
「すれ違っているけど、どうしていいか分からない」
それもそのはずです。発達が気になる子の育児は、“正解のない旅”のようなもの。
夫婦が同じ方向を向きながら歩むには、ちょっとした“道標”と“共有の地図”が必要なのです。
この記事では、現場での支援経験をもとに、発達に特性のある子を育てる中で夫婦間に生じるすれ違いの背景と、関係修復のヒントとなる7つの対処法をお伝えします。
発達が気になる子の育児で夫婦のすれ違いが増える理由

発達が気になる子どもの育児では、夫婦間の「温度差」と「役割の偏り」が原因で衝突が増えやすいです。
すれ違いが起こる原因
発達特性のある子育てでは、想像以上にエネルギーや工夫が求められます。
しかし、夫婦それぞれの育児観やストレス耐性、社会的役割(仕事・家事の負担など)には差があり、「分かってもらえない」という思いが喧嘩を引き起こします。
- 妻:「私ばっかりが調べて、対応して、疲れてる」
- 夫:「専門用語ばかりで正直わからない。仕事で手一杯だし…」
このような価値観のズレは、「協力」ではなく「対立」を生んでしまうのです。
具体例
あるご家庭では、保育園から「発達がゆっくりかもしれません」と言われたことをきっかけに、母親は相談先や療育について調べ始めました。一方、父親は「様子を見ればいい」と受け入れに時間がかかり、二人の会話はいつも平行線。やがて、会話そのものが減ってしまったといいます。

育児に対する温度差が、そのまま夫婦関係の摩擦につながります。「相手はなぜそう思うのか?」を想像することが第一歩です。
夫婦のすれ違いが長期化すると

すれ違いが続くと、育児にも支障が出る可能性があり、子どもの安心感を脅かすことにもつながります。
長期化の影響
夫婦関係の緊張は、家庭全体の空気に影響します。とくに感受性の強いお子さんは、「ママとパパがいつも怒ってる」「自分のせい?」と不安を抱きやすいのです。親自身も心が疲弊し、対応力が下がってしまいます。
具体例
「子どもが癇癪を起こすと、私と夫がどちらもイライラしてしまう。そうなると、子どもはますます不安定になって…」という母親の声もありました。負のループに陥りやすいのです。

夫婦関係は、子どもの心の土台。すれ違いを放置せず、修復のアクションを起こすことが、子どもの安心にもつながります。
夫婦のすれ違いに疲れた時の対処法7選

では、夫婦のすれ違いに疲れた時、一体どのような対応をすれば良いのでしょうか。ここでは、対処法を7つご紹介します。
① 情報を「共有」ではなく「見える化」する
夫婦間ですれ違いが起きる一番の原因は、「情報格差」です。
「こんなに大変なのに」「え?そんなこと知らなかった」――この温度差がケンカの火種になります。
例えば、療育の内容や学校とのやり取り、子どもの様子など、母親が一人で把握しているケースが多いのですが、それでは夫は“蚊帳の外”に感じがちです。
そこでおすすめしたいのが、情報の「見える化」です。
- Googleカレンダーに「療育予定・園の行事・面談」などを共有
- 子どもの様子や困りごとを、日記アプリやLINEで簡単に記録
- 家の壁にホワイトボードを設置し「今週の子どもトピック」をメモ

情報を“主観”でなく“客観”で伝えることで、夫婦間の誤解が減ります。
② 相手の「得意な分野」で役割分担する
「なんで全部私ばっかりやってるの?」
「どうやって関わればいいか分からない」
――これは“役割のミスマッチ”が起きているサインです。
夫婦が対等な関係で子育てに向き合うには、「得意なこと・できること」にフォーカスして役割を決めるのが効果的です。
- 妻:療育や行政手続きが得意 → 事務系サポートを担当
- 夫:体を使った遊びやITが得意 → 遊び&情報収集係を担当

「すべて半分ずつ」ではなく、「自分に向いていることを活かす」ことが連携のカギです。
③ 「子どもが寝たあと」は夫婦の“報告タイム”にする
子ども中心の生活に追われていると、夫婦で話す時間すら持てなくなってしまいます。
でも、意識的に“共有の時間”をつくることが、すれ違いを防ぐ最大の秘訣です。
- 毎晩10分だけ、子どもの話をする時間をつくる
- 今日の子どもの様子、困ったこと、うれしかったことを1つずつ報告
- 「今日どうだった?」とお互いに聞き合うルールに

会話の時間が短くても、“気持ちの通い合い”が夫婦の土台を支えます。
④ 相手を「正す」より「理解する」姿勢をもつ
支援現場では、「意見の違い」から夫婦関係がギクシャクしてしまうケースも少なくありません。
例えば、夫は「もっと厳しくすべき」と言い、妻は「理解が必要」と言う――意見がぶつかるのです。
でも実は、どちらも“子どものため”を思っての言葉であることがほとんど。
だからこそ、「正す」より「まず聞く」「理解する」姿勢が大切です。
- 「それは違う」→「そういう見方もあるね」
- 「なんで分からないの?」→「どう思ったか教えてくれる?」
- 「もう話したくない」→「ちょっと時間をおこうか」

小さな対話の積み重ねが、“一緒に育てる”関係をつくります。
⑤ 外部の力を「頼る勇気」をもつ
発達障害育児は、夫婦だけで完結できるものではありません。
相談支援員、療育教室、家族支援センター、SNSコミュニティ――頼れる場所はたくさんあります。
夫婦のどちらかが限界を迎える前に、「誰かに話す」「つながる」ことが大切です。
- 市町村の子育て支援センターや福祉事務所
- 発達支援センターや児童発達支援事業所
- 相談支援事業所や児童発達支援事業所
- オンラインカウンセリングなど

“夫婦間のパイプ役”を外部が担うことで、見えてくる解決策もあります。
⑥ 「ありがとう」を言葉で伝えるクセをつける
忙しい毎日の中で、一番忘れられがちなのがこの言葉です。
「ありがとう」
些細なことでも、「伝える習慣」があるかどうかで、夫婦の空気は驚くほど変わります。
- 毎日1つ、相手に感謝できたことを声に出す
- 「送迎ありがとう」「話を聞いてくれてありがとう」など具体的に
- 子どもと一緒に「ありがとうタイム」を作ってもOK

子どもの前で夫婦が感謝し合う姿を見せることも、最高の“療育”になります。
⑦ 「未来のビジョン」を一緒に描く
目の前の困りごとに追われすぎると、夫婦で“未来を語る”ことを忘れてしまいます。
でも、将来のイメージを共有することこそ、夫婦の結束を深める大きな力になります。
- 子どもが10年後にどうなっていたら嬉しい?
- 家族でやってみたいことは?
- パパ・ママとして、どんな親でありたい?

こういった対話が「同じ方向を向いている実感」を育みます。
おわりに|夫婦は“チーム”。どちらかが倒れても、立て直せる関係を

療育の現場で多くのご家族を見てきた私が、確信していることがあります。
それは、夫婦が「お互いを理解しよう」とするだけで、子どもにとっての安心感が何倍にもなるということ。
すれ違いは、どの家庭にも起こります。
でも、それを“責め合い”ではなく、“知り合い直すチャンス”に変えていく――その積み重ねが、きっと家族全体を強くしてくれます。
疲れたときは、まず自分をいたわる。そして、できるところから関係修復の糸口をつかむ。
この記事が、その一歩になれば幸いです。
こちらの記事も参考にしてください。
▶【保存版】発達が気になる子の子育てで父親ができる5つの役割
▶【子育てと仕事の両立】子供が発達障害と診断されたら仕事を辞めるべき?続けるべき?