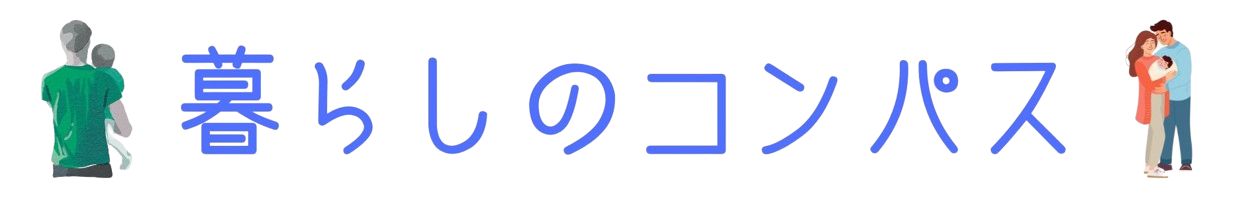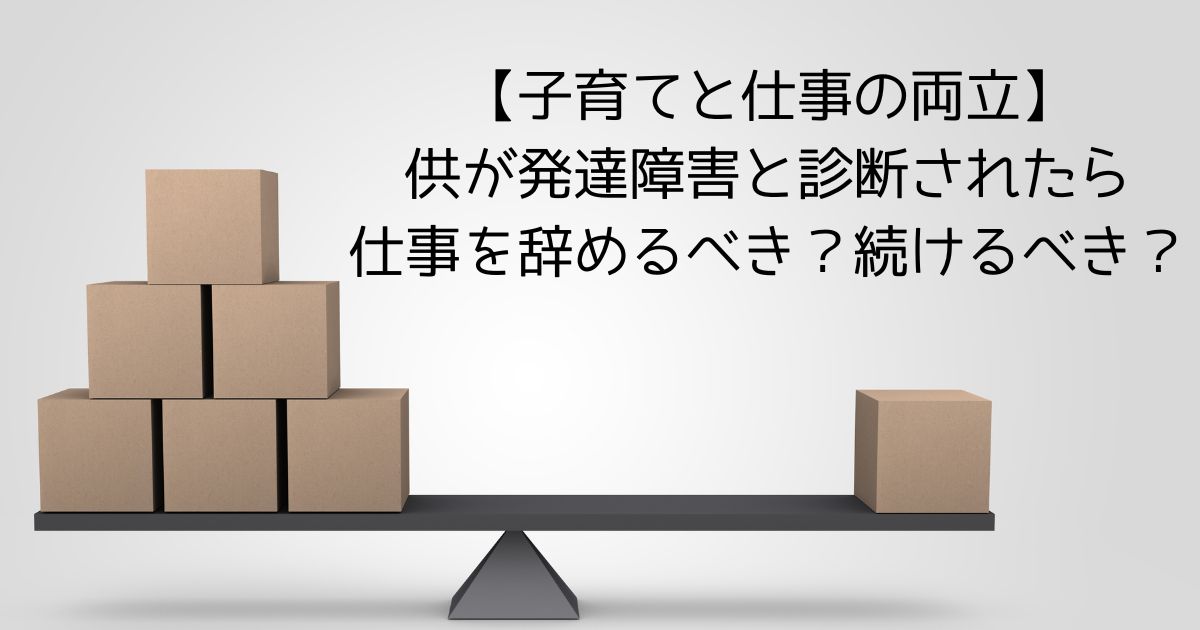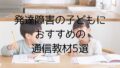「仕事を辞めるべきか悩んでいます」
「子供の療育と仕事、どう両立していけばいいの…?」
発達障害と診断された子供を育てながら働く保護者にとって、「両立」は切実なテーマです。
わが子のサポートを最優先にしたい。でも、収入やキャリア、自分の生き方も無視できない…。
この記事では、福祉現場で10年以上の支援経験をもつ筆者が、子育てと仕事を両立するための実践的なヒントをお届けします。
なぜ「子育てと仕事の両立」はこんなにも大変なのか?

発達障害のある子を育てる保護者が直面するのは、次のような現実です。
- 保育園・学校からの呼び出しが多い
- 子どもの特性に応じた対応で精神的に疲弊
- 急な呼び出しやトラブルで仕事に集中できない
- パートナーとの役割分担が不十分
- 周囲の理解が得られず孤立感がある
これに加えて、仕事では納期・会議・同僚への配慮が求められます。
“仕事か育児か”の二択を迫られるのも無理はありません。
仕事を辞める?続ける?迷ったときのチェックポイント

✔ 自分が「どれくらいの余力をもっているか」を知る
- 睡眠時間は確保できているか
- パートナーや家族の協力はあるか
- 子供のサポートにどれだけの時間が必要か
✔ 仕事の柔軟性があるか
- テレワーク・時短勤務の制度は?
- 突発的な休みに理解のある職場か?
✔ 収入と生活費のバランスは?
- 福祉サービスや手当(児童扶養手当、特別児童扶養手当等)を活用すればどうなる?
発達障害の子育てと仕事の両立はできる?

結論からお伝えすると、発達障害のあるお子さんの子育てと仕事の両立は可能です。
ただし、一般的な子育てと比べて、より高い計画性や柔軟性が求められるのも事実です。
特に以下のような課題に直面しやすい傾向があります。
- 保育園・学校との連携が必要
- 突発的な対応(癇癪・パニック等)が仕事中に発生
- 発達支援・療育など、平日日中の予定調整が必要
- 心理的・身体的負担の増加

これらの課題に対し、周囲の理解や社会資源の活用、働き方の見直しなどによって、無理なく両立を目指すことができます。
子育てと仕事の両立を助ける3つのカギ

① 福祉サービスを「フル活用」する
- 児童発達支援・放課後等デイサービスの利用で、保育+療育の両立が可能に。
- 相談支援専門員に制度や申請の相談も。
② 職場と「信頼関係」を築く
- 子供の状況を伝えすぎず、でも隠しすぎず
- 上司には「具体的な対応策」とセットで相談を
- 突発的なお迎えの時の段取りも準備しておく
③ 自分自身の「ケア」を忘れない
- ひとりで頑張りすぎない。支援者・ママ友・SNSのつながりを持つ
- 「全部ちゃんとやらなくていい」と思える余白が、子供にも伝わる
子育てと仕事を両立しながら「わが家らしい暮らし」をつくるには?

両立は、“完璧”を目指すと苦しくなります。むしろ大切なのは…
- 子供にとって「安心できる毎日」
- 保護者自身が「自分を責めすぎないこと」
- 時には「助けて」と言える力
家庭も仕事も、ゼロか100ではありません。できる範囲で調整しながら、「今のわが家にとっての最善」を見つけていけばいいのです。
実際に両立している親の声|乗り越えた壁とその工夫

ここでは、実際に子育てと仕事を両立している保護者のリアルな声をご紹介します。どれも等身大の悩みと工夫が詰まっています。
ケース1:会社員ママ(40代・小1男子の母)
「最初は療育の送り迎えとフルタイム勤務の両立に心が折れそうでした。けど、上司に事情を話して時短勤務制度を利用できるようになり、夕方の支援にも付き添えるようになりました。『伝えること』って大事ですね。」
ケース2:パート勤務パパ(30代・年中女子の父)
「娘が感覚過敏で朝の支度に時間がかかるため、毎朝大バトルでした。今は朝は僕、夜は妻と役割分担を徹底。お互いの予定も共有して、余裕を持って動けるようになりました。」
ケース3:フリーランスママ(30代・小2男子の母)
「在宅で仕事をしていると、子どもが家にいる時間にも対応しなければいけないのが逆に大変でした。時間を区切って仕事・育児のメリハリをつけるようにしたら、子どもも安心してくれるようになりました。」
どの家庭も試行錯誤しながら、「自分たちの生活スタイルに合った両立方法」を見つけています。
まとめ:子供の成長も、親の人生も、あきらめなくていい

発達障害のある子供との暮らしは、予想外の連続です。でも、その中でしか得られない喜びや絆もあります。
仕事を辞める選択も、続ける選択も、どちらも正解です。大切なのは「自分たちに合った選択をすること」。
あなたの選択が、いつか「あのとき頑張ってよかった」と思える日につながっていますように。