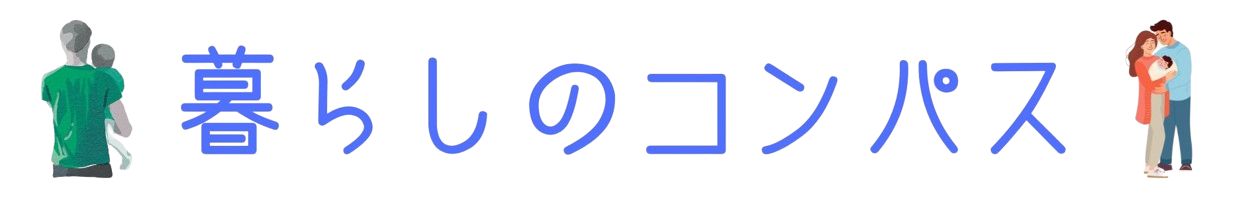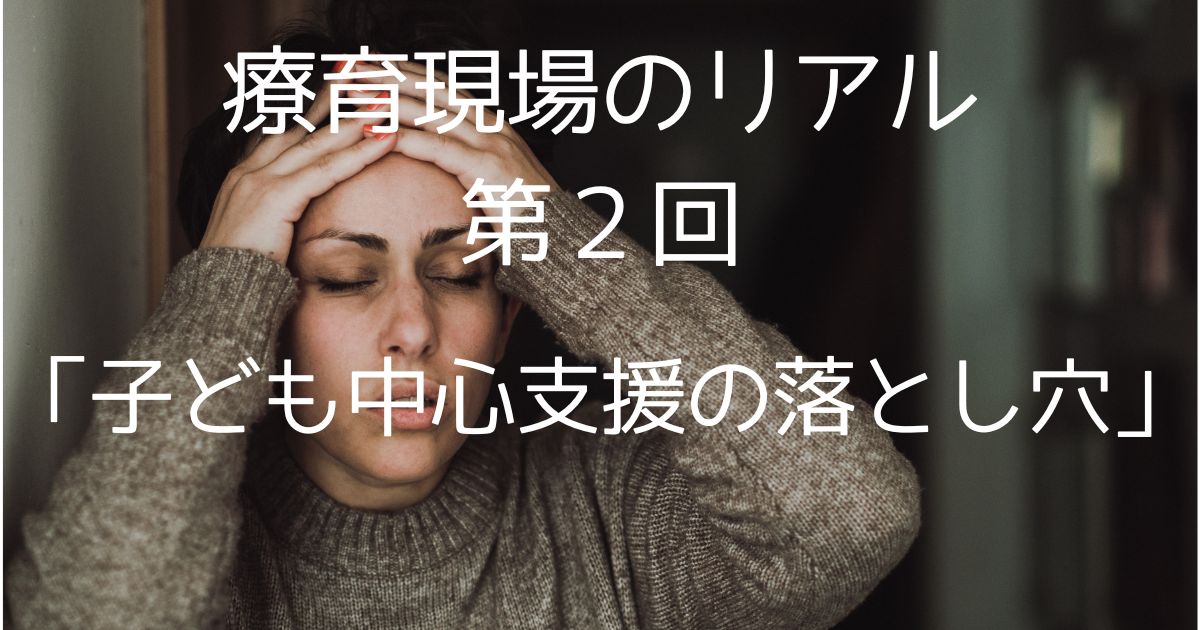こんにちは、社会福祉士のまっさんです。
前回の記事では、「療育は子ども支援だけではなく、家族全体を支えるもの」という視点をお伝えしました。今回はさらに一歩踏み込み、「困っている保護者への支援」に焦点を当ててお話します。
「子ども中心」は正解? でも、いつも正義とは限らない
療育現場の多くは、「子どもを中心に考える」ことを大切にしています。
子どもにとっての最善を考え、発達課題に応じた支援計画を立てる。これは専門職として当然の姿勢です。
しかし——現場で支援を続けていると、ふと立ち止まらざるを得ない場面に出会います。
「この支援、本当に家庭で続けられるのか?」
「子どもが成長するほどに、親の負担が増していないか?」
子どもを中心に据えた支援が、結果的に保護者を孤立させたり、疲弊させたりしているケースがあるのです。
保護者の“困りごと”は、声にならない
私たちがよく出会う保護者の言葉に、こんなものがあります。
- 「これがうちの子に合うのはわかってるんです。でも家じゃできないんです」
- 「先生の前では頑張れるけど、家では癇癪がすごくて…」
- 「園からの連絡帳を見るのが怖いんです」
こうした声の裏には、「子どもにとって良いことを、実行できない自分」を責める気持ちが隠れています。
保護者は、日々子どもの特性と向き合いながら、仕事や家事、きょうだい児の世話も抱えています。
にもかかわらず、「家庭でもこのアプローチを続けてください」「自己肯定感が大事です」と言われ続けたら、誰だって疲れますよね。
寄り添いとは、アドバイスを減らすこと
私が大切にしている支援スタンスは、とてもシンプルです。
“わかってくれる人がひとりでもいれば、親は立ち上がれる”
そのために、アドバイスよりも共感。
専門用語よりも、生活の言葉。
予定されたプログラムよりも、その日の親の表情を大事にします。
たとえばこんな関わり方をします。
- 「今日、ここに来るだけで大変でしたよね」
- 「夜中に起きちゃうって、保護者の方も全然寝れてないですね」
- 「それ、すごくしんどかったですよね」
共感されることは、心の安全基地になる。
その“安全基地”ができて初めて、家庭でも支援が回り始めます。
支援が「義務」になってはいけない
「親がちゃんと取り組めば、この子はもっと伸びる」
「家でもトレーニングをしてほしい」
——そんな気持ちが、いつしか“圧力”になってしまうこともあります。
でも私たち専門職が見なければいけないのは、「今、この親にできる現実的な支援は何か?」という視点。
時には、「しばらく家では何もしないで、親子で好きなことだけして過ごしましょう」と提案することもあります。
支援は“義務”ではなく、“選べる選択肢”でなければなりません。
その選択肢を増やすことが、支援者の役割です。
子どもと親、両方が安心して育てる環境づくりへ
「困っているのは子どもだけじゃない。親も、困っている。」
この当たり前の事実が、療育現場では見落とされがちです。
子どもにとって大切なのは、スキルの習得ではなく、安心して“ありのまま”でいられる時間。
そしてその時間は、保護者が安心して子どもと向き合える時にだけ生まれます。
さいごに|親を支えることで、支援は前に進む
支援のプロとして子どもの成長を願うのは当然です。
でも、「親が疲れ果てているなら、その支援は意味を成さないかもしれない」という視点を持つこと。
これこそが、社会福祉士としての私の信念です。
療育は、家庭に根を張る支援。
子どもと、親と、その両方に手を差し伸べることが、未来につながると私は信じています。
次回予告:「第3回 “わかってもらえない”孤独|相談できない保護者の背景にあるもの」
支援を届けたいけど、うまく届かない。沈黙の中にある親の葛藤を見つめます。