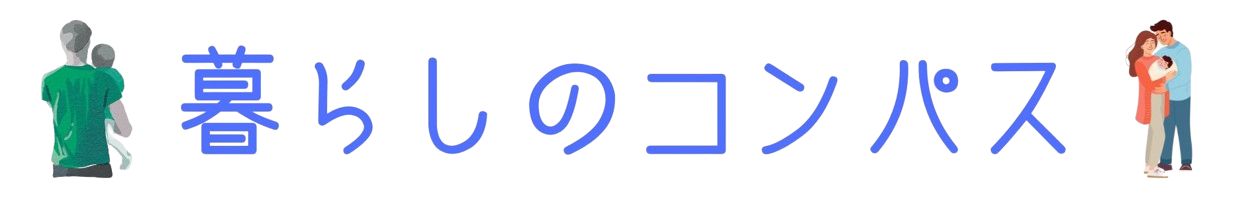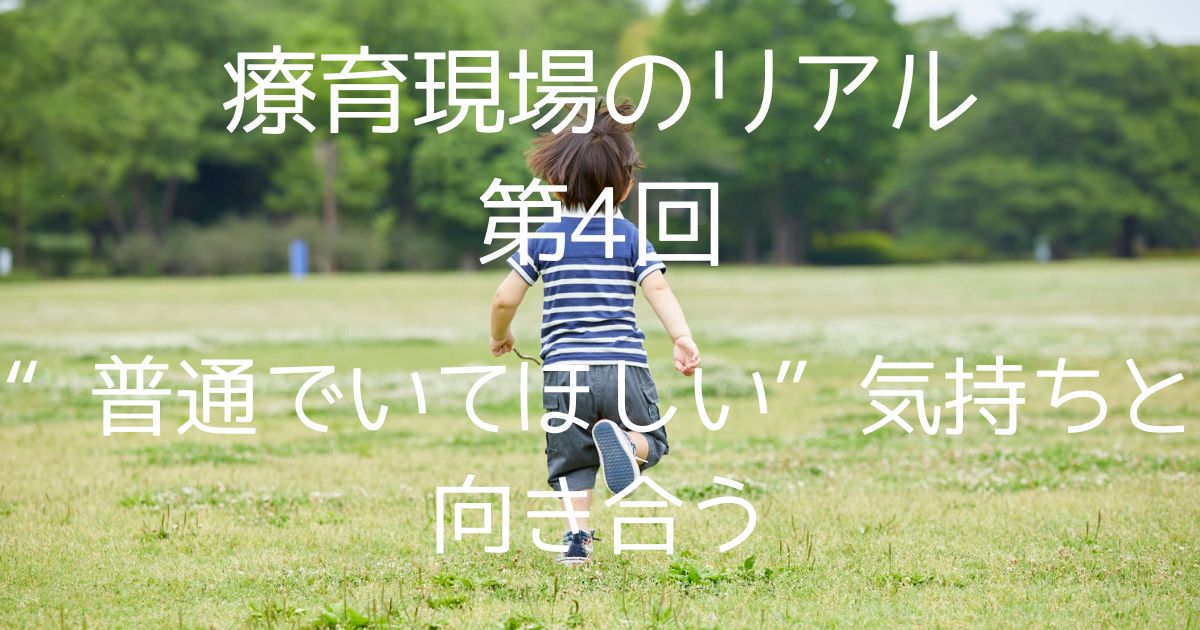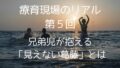こんにちは。社会福祉士のまっさんです。
この連載では、療育の現場から見える「家族支援」のリアルをお届けしています。
今回は、保護者の心の奥にある、「普通でいてほしい」という気持ちに焦点を当てます。
「普通になってほしい」と願う親心は悪なのか?
「障害があるとは思いたくない」
「他の子と同じように育ってほしい」
「“普通”の子と同じ小学校に通って、“普通”に生きてほしい」
療育の相談場面で、こうした声に触れることは少なくありません。
そして、多くの保護者はその気持ちをどこか“いけないこと”のように感じて、自分を責めています。
しかし、私はこう考えます。
「その気持ちは、とても自然で正直なものです」と。
“普通”とは何か?私たちが無意識に信じている「基準」
日本社会において、「普通」はとても強い力を持っています。
- 集団にうまくなじめること
- 友達と同じように行動できること
- 一斉指示が理解できること
- 小中高と進学して、就職すること
これらが“当たり前”とされる文化の中で、発達に特性のある子どもを育てる親は、絶えず「普通」との比較の中に置かれます。
そして、ふとした瞬間に湧いてくるのが、
「うちの子も、普通だったらよかったのに…」という想い。
「普通になってほしい」は、実は“愛情”のかたち
この気持ちを否定するのは簡単ですが、実はとても深い愛情から来ているのです。
- 社会の中で孤立してほしくない
- 苦労の少ない人生を歩んでほしい
- 他人と比べて自信を失ってほしくない
つまり、「普通でいてほしい」という気持ちは、
“この子が少しでも生きやすくありますように”という願いの裏返しなのです。
しかし、「普通」を追い求めることで起きるすれ違い
一方で、「普通」を基準にした関わりは、子どもにとって大きなプレッシャーになります。
- 本当は苦手なことを我慢してやらされる
- できない自分に劣等感を抱く
- 自分らしさより「合わせること」が大事になる
すると、親子の関係にもすれ違いが生まれます。
「頑張ってるのに、わかってもらえない」
「うちの子はわがままなのかも」
「何が“正解”なのか、わからない…」
このように、お互いが苦しくなってしまうのです。
社会福祉士として伝えたい「普通以外の幸せの形」
支援の場面で私がよく使う言葉があります。
「“普通”に合わせるより、“その子に合った道”を見つけることが大事ですよ」
もちろん、親として“普通”を望む気持ちは理解した上で、「他の道でも幸せになれる」ことを丁寧に伝えていきます。
合理的配慮があることで、得意が輝く
たとえば、静かな場所で学べば集中できる子もいます。
ビジュアルで説明されれば理解できる子もいます。
特性に合った環境があれば、“その子らしさ”が生きてくるのです。
社会の価値観は少しずつ変わってきている
インクルーシブ教育や、障害理解の広がり、特性を活かした就労の場も増えています。
“普通”を目指すより、「本人が自信を持てる環境をどう整えるか」が、今の支援の焦点なのです。
“普通でなくてもいい”と思えるようになるには?
もちろん、頭では理解していても、心が追いつかないこともあります。
焦らなくていい
「“普通”を手放す」ことは、時間がかかることです。たとえば喪失体験と同じように、受け入れには段階があります。
- 否認 → 怒り → 取引 → 抑うつ → 受容
このプロセスを、親自身が辿っていくことが多いのです。
だからこそ、支援者は“焦らせない”ことが大切です。
安心して話せる場があるかどうか
自分の気持ちを語れる場があると、心が整っていきます。
「そんなふうに思うの、私だけじゃなかった」
この共感が、次の一歩を後押しします。
最後に|“普通”よりも、“その子のしあわせ”を一緒に見つけていく
療育や支援のゴールは、「普通」に近づけることではありません。
子ども自身が、自分らしく生きられる環境を整えることです。
そのためには、まず保護者が「普通」に縛られずに、「わが子らしさ」に目を向けることがスタートです。
支援者は、“普通を目指す苦しさ”に寄り添いながら、“違っても大丈夫”と伝えていく役割を担っているのだと、日々感じています。
関連記事はこちら
⇒第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
⇒第2回 困っている親に寄り添うという支援|子ども中心支援の落とし穴
⇒第3回 “わかってもらえない”孤独|相談できない保護者の背景にあるもの