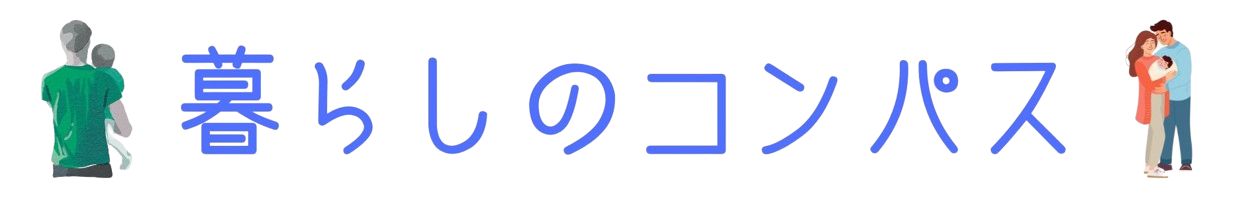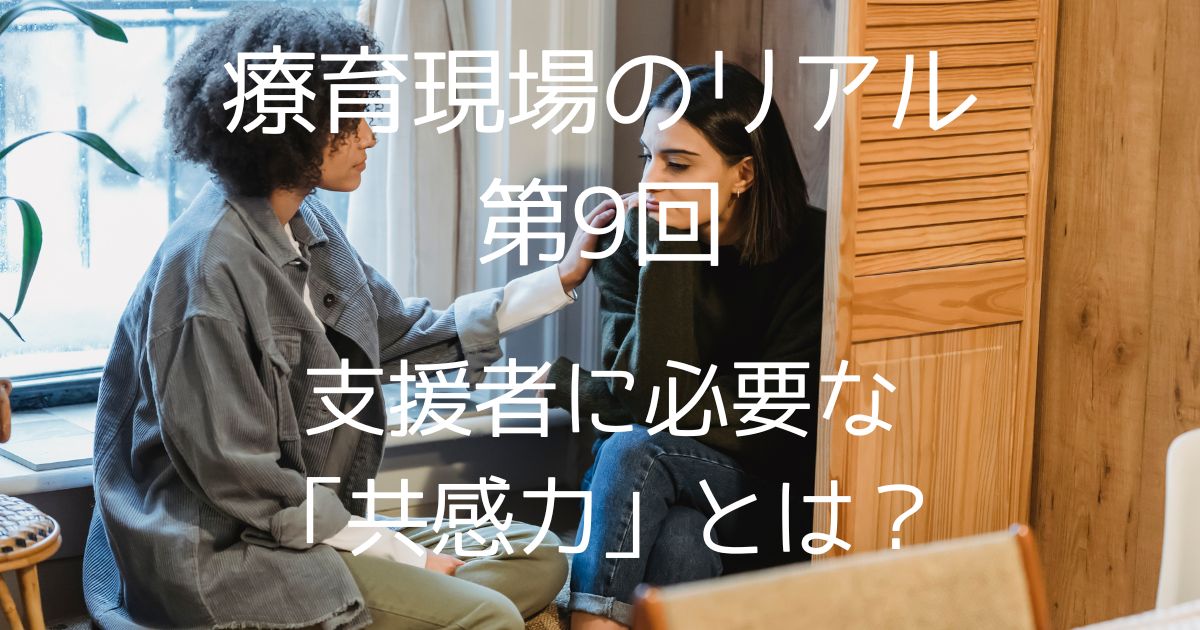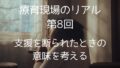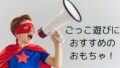こんにちは、社会福祉士のまっさんです。
療育の現場で日々子どもや保護者と関わる中で、「正しいはずなのに、伝わらない」「むしろ、距離ができてしまった」と感じたことはありませんか?
今回のテーマは、「正しさ」と「共感力」の関係。
支援者として持っておくべき知識や技術は確かに大切です。でも、“正しいこと”が必ずしも“相手を支えること”にはならないという現実も、私たちは理解する必要があります。
正しさが“壁”になるとき
ある日、初めて相談に来たお母さんが、涙ぐみながら言いました。
「この子には“発達障害の可能性があります”って言われました。でも、そんな風に決めつけられて、どうしたらいいか分からなくて…」
支援者としては、早期支援につなげるために「必要な情報」を伝えたつもりでも、当事者の心は「傷つき」「拒否された」と感じていることがあります。
これは、知識が間違っているのではなく、「伝え方」や「タイミング」、そして「相手の気持ちへの配慮」が不足していたことが原因なのです。
支援者にありがちな“正しさの押しつけ”
こんな言葉、言ったことはありませんか?
- 「このまま放っておくと将来もっと困りますよ」
- 「専門家の言うことを信じてやってみてください」
- 「今の関わり方が、よくないんです」
これらはすべて、事実に基づいている「正しい言葉」です。
でも、今の保護者にとって受け止められる準備ができていなければ、正しさは暴力になってしまうのです。
「共感力」が支援のカギを握る理由
共感とは、相手の気持ちに寄り添い、その感情の背景を想像し、否定せずに受け止めること。
これは「かわいそうだと思うこと」や「同じ気持ちになること」とは違います。
大切なのは、相手がそう感じていること自体を否定せず、受け止める姿勢です。
共感を持って関わると、こんな変化が生まれます。
- 保護者が「話してもいい」と思える関係性が育つ
- 提案に対する信頼感が生まれる
- 「わかってもらえた」という経験が、支援の継続につながる
支援の中で「共感力」を発揮する工夫
1. まずは“気持ちの確認”から始める
「突然のことで、びっくりされたと思います」
「どう感じられたか、お聞きしてもいいですか?」
相手の気持ちを言語化する手助けをすることで、心の整理が始まります。
2. アドバイスより“気持ちの共有”を優先する
「大変な中でも、こうして相談してくださってありがとうございます」
「それだけ、お子さんのことを大切に考えていらっしゃるんですね」
気持ちが受け止められることで、「聞く耳」が開かれます。
3. “同じ土俵”に立つ姿勢を示す
支援者だからといって“上から”にならないよう、自分も迷う存在であることを伝えることで、信頼関係は深まります。
まとめ|「正しさ」よりも「伝わる支援」を
支援の現場で求められるのは、「専門性」と「共感性」の両立です。
どれだけ医学的・発達的に“正しい”情報であっても、相手に伝わり、受け取ってもらえなければ意味がないのです。
共感力は、相手を変えるためのツールではなく、「相手の世界に足を踏み入れる覚悟」から生まれるもの。
そのうえでこそ、本当に必要な支援や提案が“生きたもの”として届くのです。
次回は、「【第10回】「うちの子だけ違う…?」親が抱える“見えない孤独”に寄り添う」──子どもの発達に悩む保護者の多くが抱える“孤立感”。その背景にある「言葉にならない不安」とは?社会福祉士ができる支援のヒントを探ります。
関連記事はこちら
▶第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
▶第8回 “支援を断られた”ときの意味を考える|不信感の裏にある本当の気持ちとは?