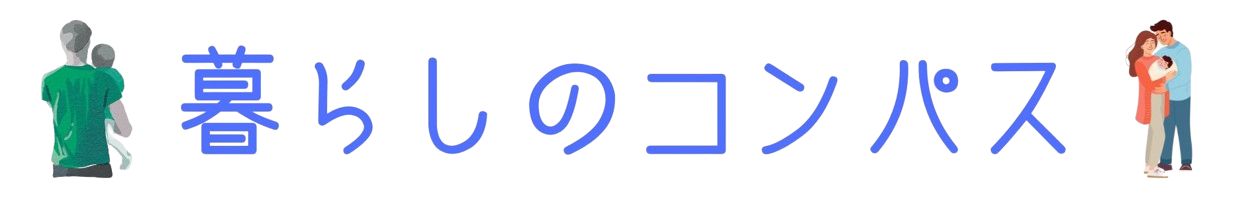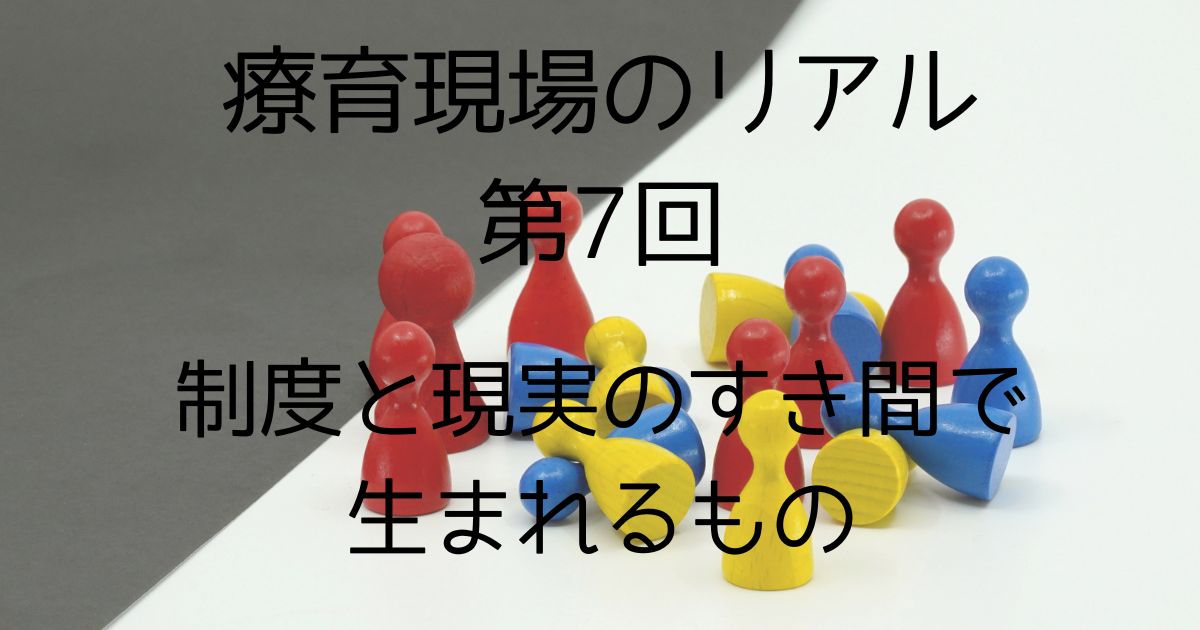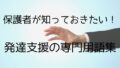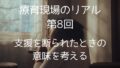こんにちは。社会福祉士のまっさんです。
この連載では、療育の現場に携わる支援者として、実体験と気づきを綴っています。
今回は、「制度と現実のズレ」について取り上げます。
制度に沿って支援しているのに、どこか“しっくりこない”──そんな場面に、あなたも出会ったことがあるのではないでしょうか。
マニュアル通りに進まない“現実”
療育には、国の制度や自治体のガイドライン、支援計画など、一定の「枠組み」があります。
しかし、現場ではその枠からこぼれ落ちるニーズが、必ず存在するのです。
たとえば──
- 「療育の時間だけでは足りない」と感じている親
- 「枠組みに当てはまらない」グレーゾーンの子ども
- 「形式的なモニタリングでは実態が見えない」と感じる支援者
制度が整っていても、“今ここ”の声に完全に応えられない瞬間は、日常のように訪れます。
「違和感」は現場からのサイン
現場で感じるモヤモヤや「なんか変だな…」という感覚は、
支援者の感性が働いているサインです。
たとえば、
- 「この家庭、計画上は順調だけど、何か話せていない気がする」
- 「この子にとって、この支援は本当に楽しいのかな?」
- 「制度は通っているけど、この人にとって本当に必要な支援は別の部分にあるのでは?」
こうした“違和感”にフタをしてしまうと、本質的な支援から遠ざかってしまいます。
むしろその違和感こそが、「支援の軌道修正」のきっかけになるのです。
現場のエピソード:「お母さんの涙が止まらなかった日」
ある日の面談で、支援計画の更新に関する説明を行ったときのこと。
書類通りに進め、必要なサービスもついていたのに、お母さんの目からぽろっと涙がこぼれました。
「…誰にも言えなかったけど、私、最近ずっと“頑張らなきゃ”って張り詰めてたんです」
その瞬間、私の中にあった「この家庭は安定している」という前提が崩れました。
──形式上は整っていた。でも、“支えられている感覚”にはつながっていなかった。
制度上の支援と、心に届く支援には、時として乖離がある。
それを教えてくれた大切な出来事でした。
支援者が制度を“使いこなす”という視点
制度は、支援者にとって「制限」ではなく、「道具」であるべきです。
大事なのは、“制度に人を合わせる”のではなく、“人に制度を合わせる”視点。
たとえば…
- 加算要件に縛られすぎず、ニーズ本位で柔軟に支援メニューを構成する
- 記録やモニタリングを、“意味ある対話”の時間に変える
- 制度の枠外で困っている家庭がいれば、地域資源や任意支援を提案する
こうした“制度のすき間を埋める力”こそ、現場の支援者が持つ強みです。
違和感を持ち寄れるチームづくりを
一人で抱える“モヤモヤ”は、しばしば「気のせい」と片づけられてしまいます。
でも、支援チームの中で共有すれば、気づきが行動につながるチャンスになります。
- 「こう感じたんだけど、他の人はどう思う?」
- 「このケース、何か引っかかってるんだけど…」
- 「この制度運用、現実に合ってるのかな?」
違和感を安心して話せる場づくりは、支援の質を底上げします。
“感じる力”を尊重し合えるチームは、利用者にとっても安心できる場になるのです。
保護者へのメッセージ:「違和感」は伝えてもいい
保護者の皆さんも、どうか“気になること”を伝えてください。
- 「この支援、合ってる気がしない」
- 「もっと話したいことがある」
- 「制度のこと、よくわからない」
──そんな言葉が支援者を動かします。
制度の限界や運用の難しさも正直に話し合える関係が、本当に届く支援を生み出す第一歩です。
おわりに|「違和感」から始まる支援の可能性
“正しさ”だけでは救えないものが、療育の現場には確かにあります。
だからこそ、支援者が感じた「違和感」や「なんとなくの不安」を信じることは、とても重要です。
制度は整っていても、それだけで十分ではありません。
現場で生まれる“ちいさなひっかかり”こそ、
私たちが子どもと家族にもっと近づくためのヒントなのです。
次回は、「【第8回】“支援を断られた”ときの意味を考える|不信感の裏にある本当の気持ちとは?」──支援を提案しても、拒否されたり距離を置かれたりする場面。その裏にある、保護者の本音や過去の傷つきをどう受け止めるのかを考えます。
関連記事はこちら
▶第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
▶第6回 支援者も迷っていい|「正解がない」療育の現場から見えてきたこと