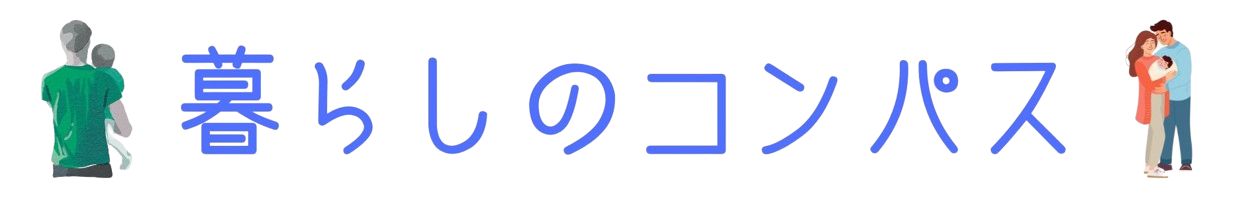「うちの子、まだごっこ遊びしないけど大丈夫?」「いつから始まるものなの?」
こんな不安を感じていませんか?
子どもの成長に欠かせない「ごっこ遊び」は、実は社会性・想像力・言葉の発達と密接に関わっています。
この記事では、発達支援の現場で10年以上子どもたちに関わってきた社会福祉士の視点から、ごっこ遊びが始まる時期や、遊び方の特徴、年齢別の支援アイデアをご紹介します。
ごっこ遊びはいつから?|発達の目安と個人差

厚生労働省の「保育所保育指針解説書」によると、ごっこ遊びができるようになるのは「おおむね2歳頃から」とされています。
療育現場においても、ごっこ遊びの芽は、1歳半〜2歳ごろから見られることが多く、3歳ごろには本格的に始まります。ただし、すべての子が同じように進むわけではありません。
| 年齢 | ごっこ遊びの特徴 | よくある行動の例 |
|---|---|---|
| 1歳半〜2歳 | 模倣遊びの始まり | ぬいぐるみに食べさせる仕草 |
| 2歳〜3歳 | 単純なごっこ遊び | お医者さんごっこ、ままごとなど |
| 3歳〜4歳 | 役割交代や会話が加わる | 「私はママね、あなたは赤ちゃん」 |
| 4歳以降 | ストーリー性のある遊び | 複数人でのやりとり、空想の展開 |
● 1〜1歳半頃:モノまね遊びのはじまり
この時期は、周囲の大人の行動を真似して楽しむ「模倣遊び」が中心です。たとえば、ママがスマホを使っているのを見て、自分もおもちゃの電話で話すフリをするなどの姿が見られます。
● 2歳〜2歳半:簡単なごっこ遊びへ
人形にごはんを食べさせる、お布団をかけるなど、単一のシーンを再現する遊びが始まります。「○○ちゃんもねんねするよ~」といった言葉とともに行動することも。
● 3歳〜4歳以降:ストーリー性のあるごっこ遊び
役割分担をして「お店屋さんごっこ」「ヒーローごっこ」などが楽しめるようになります。お友だちとのやりとりの中で、順番を待つ、相手の気持ちを考えるといった社会的スキルも育ちます。

「まだやらないから発達が遅れているのでは?」と心配する必要はありません。子どもによって興味や得意分野が違うため、ごっこ遊びに入る時期も個人差があります。
ごっこ遊びと社会性の関係

ごっこ遊びは、単なる遊びではなく、以下のような重要な発達スキルを育てます。
- 共同注意(同じものに注目し、やりとりを楽しむ)
- 想像力と柔軟な思考
- 他者の立場を想像する力(視点取得)
- 自己表現・自己調整能力
特に、発達障害のあるお子さんの場合、これらのスキルを伸ばす支援的なごっこ遊びはとても効果的です。
ごっこ遊びが苦手な子の特徴と背景

ごっこ遊びに興味を示さない背景には、以下のような要因が関係している場合があります。
- 感覚過敏・鈍麻:衣装や素材に不快感があると遊びに集中しにくい。
- 言葉の発達の遅れ:想像を言葉でやりとりする力が未発達。
- 共同注意が育っていない:相手と「一緒に楽しむ」という視点が難しい。
- 遊びの意味がわかりづらい:リアルとフィクションの区別が曖昧。
こうした場合は、遊びの前提となる力(模倣・共同注意・言語)を支援しながら、焦らず関わることが大切です。
ごっこ遊びが苦手な子への関わり方

① 興味に寄り添う
好きなキャラクターや動物などを題材にした遊びから始めると、興味を持ちやすくなります。
② モデルを見せる
最初は大人が「こんなふうにするんだよ~」と、楽しくやってみせることが効果的です。
③ 絵本や動画を活用する
ストーリー性のある絵本や動画は、ごっこ遊びの“ヒント”になります。登場人物のやりとりを真似するところからスタートしましょう。
④ 無理に誘わない
「遊びたくない」と感じているときに無理強いすると、逆効果です。「見てるだけ」でもOK!
年齢別・支援のヒントと遊びのアイデア

● 1〜2歳:まねっこがごっこ遊びの入口
- 一緒にやって見せる(大人が「食べさせるふり」など)
- 音の出るおもちゃ・ぬいぐるみで感覚的に楽しむ
- 言葉を添える「ワンワン、あーんしてね」
● 2〜3歳:簡単な役割を楽しむ
- お医者さんセット、おままごとセットを用意
- 「どっちがママする?」と役を提案
- 動作を真似るだけでOK、無理に話させなくても◎
● 3〜5歳:複数人でストーリーを作る
- ストーリーカードや場面づくりができるおもちゃ(例:プレイハウス)
- 「昨日の続きをしようか?」と前日とのつながりを意識
- お友だちとのトラブルを通じて社会性も育つ
よくある質問Q&A

Q. ごっこ遊びが全然できません。発達に問題がある?
A. まだ準備ができていない段階かもしれません。模倣や共同注意、感覚の心地よさなど基礎的な力を育むことから始めましょう。
Q. 一人っ子なので相手がいません。
A. 保護者が相手になって「一緒に遊ぶ」だけでも十分です。ぬいぐるみに語りかける、一人遊びでも空想があれば立派なごっこ遊びです。
保護者のリアルな声|ごっこ遊びの変化

「最初はごっこ遊びをしてくれなくて心配でしたが、アンパンマンのレジを買ったら、少しずつ“いらっしゃいませ”と言えるようになってビックリしました」(4歳・男の子のママ)
「お世話人形を通じて、“いたいのいたいの飛んでけ~”と言えるようになり、優しい気持ちが育っているのを感じます」(3歳・女の子のパパ)
まとめ
ごっこ遊びは、「遊び」でありながら、子どもが人との関係性を学び、感情を表現し、言葉やルールを身につけていくための大切な土台です。
無理にやらせるのではなく、環境や関わりの工夫で自然と引き出すことが鍵となります。「できない」ではなく「これから育っていく力」として、ぜひ温かく見守ってください。
関連記事はこちら
▶ごっこ遊びにおすすめのおもちゃ10選