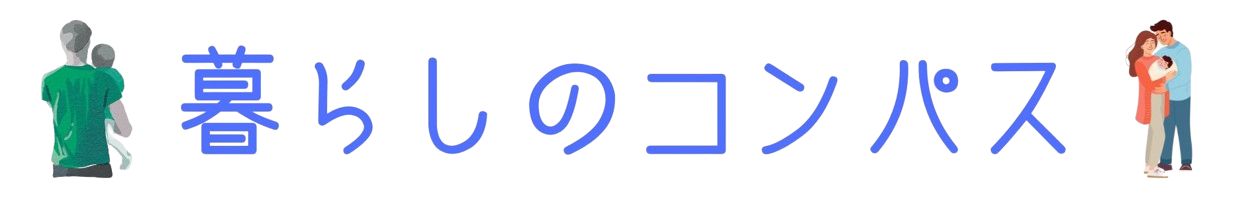障害のある子どもの支援に日々向き合う中で、ふと感じたことがあります。
それは、「そのきょうだいたち(=きょうだい児)の想い」は、どこまで届いているのだろう?ということです。
障害のある子に注目が集まりやすい家庭や支援環境において、きょうだい児は“良い子”であろうと頑張り、自分の気持ちを抑え込むことが少なくありません。
- 「ママを困らせちゃいけない」
- 「僕が我慢すればいい」
- 「どうして、あの子ばかり…?」
そんな“言葉にならない気持ち”に、やさしく寄り添ってくれるのが絵本です。
この記事では、福祉現場での経験をもとに、きょうだい児の“気持ちに寄り添う”絵本10選をご紹介します。
年齢別に分類しながら、絵本を使った声かけのコツや活用法もあわせてお届けします。
きょうだい児とは?|障害のあるきょうだいと暮らす子どもたちの現実

きょうだい児が抱えやすい気持ち
「きょうだい児」という言葉は、障害のある子どもや医療的ケア児の“きょうだい”を意味します。
一見、健やかに見える彼らも、家庭内でこんな気持ちを抱えていることがあります。
- 寂しさ:もっと話を聞いてほしい、甘えたい
- 嫉妬・罪悪感:どうしてあの子ばかり?でもそんなふうに思っちゃいけない
- 不安・プレッシャー:自分がしっかりしなきゃいけない
これらの感情は、成長する中で自覚されにくく、周囲にも伝えづらいものです。
なぜ絵本がきょうだい児支援になるのか?
絵本は、きょうだい児の「心の通訳」になります。
- 言葉にしづらい気持ちを物語に代弁してもらえる
- 感情を「客観的に眺める」体験ができる
- 親子の対話のきっかけになる
何気ない読み聞かせの時間が、子どもたちにとって「自分も大切にされている」と感じられるかけがえのない時間になることがあります。
【3〜5歳向け】兄弟児へのおすすめ絵本 3選
① 『わたしのワンピース』(こぐま社)
- おすすめポイント:空想の世界が広がる一冊。自由な発想と“自分らしさ”を楽しむ内容が、自己肯定感を育みます。
- こんなときに:弟や妹が注目されているときに。
🗣 声かけ例:「あなたの好きな模様のワンピースはどれだろうね?」
② 『ちょっとだけ』(福音館書店)
- おすすめポイント:妹が生まれたお姉ちゃんが「ちょっとだけ」我慢する姿と、それをちゃんと見ているママの姿に共感が集まる感動作。
- こんなときに:「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんだから」と言ってしまった後に。
🗣 声かけ例:「あなたも“ちょっとだけ”頑張ってるよね、ママわかってるよ。」
③ 『にじいろのさかな』(講談社)
- おすすめポイント:与えることの喜び・寂しさを描いた名作。兄弟との関係に悩むときのヒントに。
- こんなときに:弟や妹とのトラブル後に。
🗣 声かけ例:「あなたのキラキラ、誰かにあげたことあるかな?」
👧 【6〜8歳向け】兄弟児へのおすすめ絵本 4選
④ 『ぼくのニセモノをつくるには』(偕成社)
- おすすめポイント:完璧でいようとする子どもに、「自分らしくていい」と伝える一冊。兄弟児の“いい子願望”をほぐす内容。
- 感情ポイント:頑張りすぎる子へのメッセージとして。
🗣 声かけ例:「“あなたにしかできないこと”ってあるね。」
⑤ 『わたしがいどんだ戦い 1939年』(評論社)
- おすすめポイント:足の不自由な妹と暮らす少女の葛藤と成長を描く感動の長編絵本。共感性・深い理解を促す。
- 中学年向け:読んで感じたことを話し合う読後体験が◎。
⑥ 『ふたりはともだち』(文化出版局)
- おすすめポイント:兄弟ゲンカや仲直りのリアルを描いた一冊。兄弟の存在を“あたたかく”見直せるきっかけに。
⑦ 『おこだでませんように』(小学館)
- おすすめポイント:怒られがちな男の子の本音に、大人も胸が締めつけられる絵本。家庭の“安心感”を考えるきっかけに。
🧒 【9歳以上・思春期向け】兄弟児に響く絵本 3選
⑧ 『いつでも会える』(学研)
- おすすめポイント:別れと再会、心のつながりを描いた絵本。死や障害への“不安”を優しく包み込む。
⑨ 『あなたのことがだいすき』(角川書店)
- おすすめポイント:そのままのあなたが大好きというメッセージを伝える、シンプルながら深い愛情が詰まった一冊。
⑩ 『こどもたちはまっている』(亜紀書房)
- おすすめポイント:「ちゃんと見ていてほしい」子どもの本音に、大人が気づかされる一冊。自己肯定感を高めたいときに◎。
きょうだい児に絵本を読むときの3つのポイント

1. 無理に読ませない
「さあ読むよ」と押し付けず、自然なタイミングで手渡しましょう。
2. 読み終わった後の会話が宝物
「どう思った?」「誰が好き?」と感想を聞くだけで、気持ちが解放されやすくなります。
3. 感情を正解・不正解で決めない
たとえ「うらやましい」「嫌い」といった感情でも、受け止めることで自己肯定感が育まれます。
親ができる“きょうだい児支援”は、完璧じゃなくていい

保護者の多くが、「きょうだい児をちゃんと見てあげられていないのでは」と罪悪感を抱えています。
でも大切なのは、「全部は無理でも、ちょっとずつ伝えていくこと」。
- 「あなたの気持ちも知りたいよ」
- 「よく頑張ってるね」
- 「一緒に絵本読もうか?」
そんなひと言が、子どもにとって大きな安心になります。
まとめ:絵本の活用で“心の居場所”を家庭に
きょうだい児にとって絵本は、
「気づかれなかった気持ちを代わりに伝えてくれる存在」です。
ポイントは、「読み聞かせの時間を“特別なひととき”にすること」。
毎日でなくても構いません。一緒に絵本を読むことで、“あなたのことを大切に思っている”というメッセージが、しっかりと伝わります。
今日も一冊の絵本から、小さな対話を始めてみませんか?
【あわせて読みたい】
・【支援】きょうだい児が抱える悩み・気持ちに寄り添うためにできる10のこと
・【本音で語る】きょうだい児支援に疲れたら|がんばりすぎないための7つの視点
・【プロ厳選】療育グッズおすすめ10選|家庭で使える知育アイテムを徹底比較