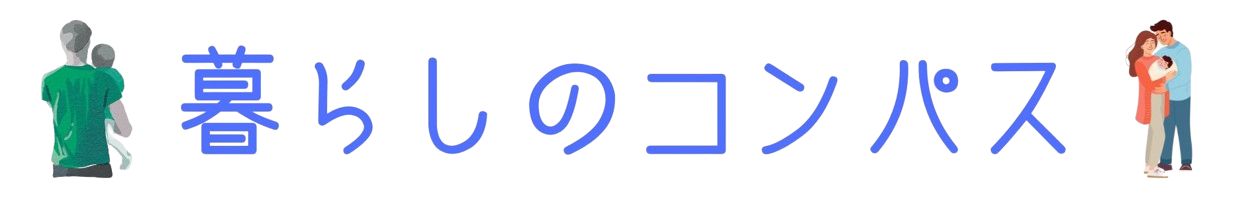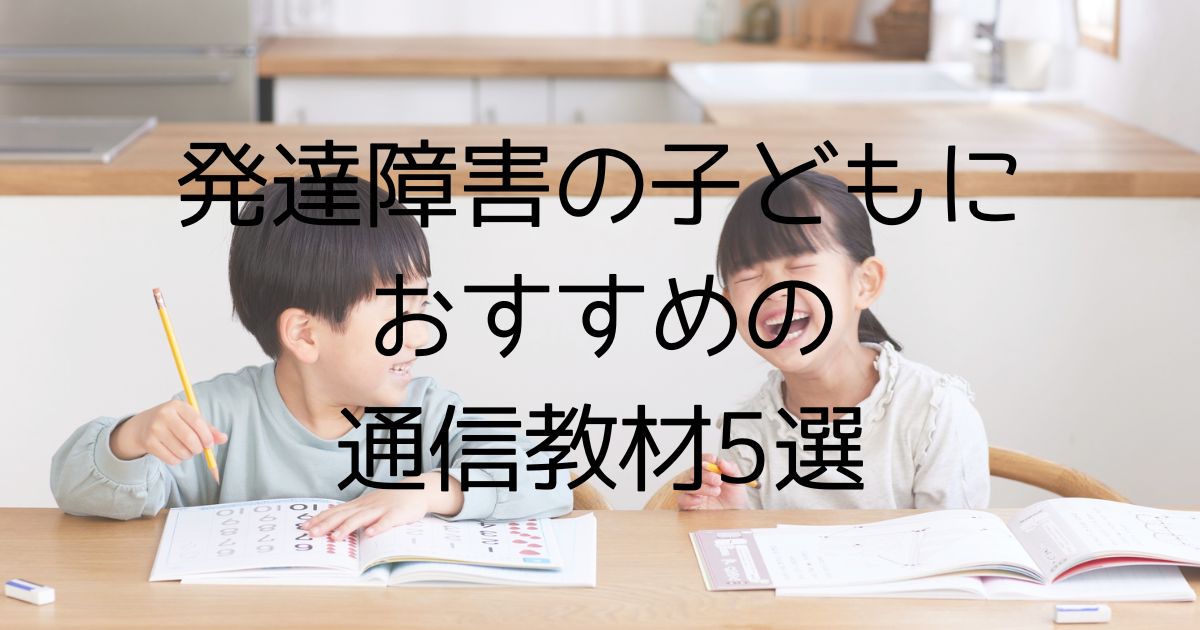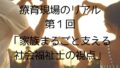発達障害のあるお子さんを育てていると、「家でもできる支援ってないのかな?」「療育に通えない日も何か取り組ませたい」と感じることはありませんか?
特に仕事や育児で忙しいご家庭では、毎日療育の時間を確保するのが難しいという声もよく聞きます。
そんなとき、役立つのが【通信教材】です。
通信教材は、家庭にいながらお子さんの発達を支援できる便利なツール。
しかも最近では、発達障害の特性に配慮された教材が増えており、「視覚でわかりやすい」「段階的で無理がない」「やる気を引き出す仕組みがある」など、続けやすい工夫がたくさん。
今回は、発達障害の特性に配慮された【おすすめの通信教材5選】をご紹介します。
家庭療育のひとつの選択肢として、ぜひ参考にしてください。
発達障害の子どもが勉強や学習で悩みやすいこと

発達障害のある子どもが勉強で悩みやすいポイントは、その子の特性によって異なりますが、以下のような困難がよく見られます。
1. 集中が続かない(ADHD傾向)
- 数分で気が散ってしまう
- 周囲の物音や人の動きが気になりすぎる
- 宿題に取りかかるまでに時間がかかる
🟡 例:「5分も机に座っていられない」「問題は解けるのに途中で飽きてやめてしまう」
2. 読み書きが極端に苦手(LD・ディスレクシアなど)
- 文字を読むのにすごく時間がかかる
- 音読になると間違いが増える
- 書くのに手が疲れやすい、鏡文字になる
🟡 例:「黒板の文字をノートに写せない」「漢字を覚えてもすぐに忘れる」
3. 話の流れがつかめない・指示が通りにくい(ASD傾向)
- 抽象的な言葉やあいまいな指示が理解できない
- 文脈をつかむのが苦手
- 長い説明を一度に聞くと混乱する
🟡 例:「先生の説明を聞いても、何をすればいいかわからない」
4. 不安が強く、新しいことに取り組みにくい(ASD・HSC傾向)
- はじめての課題やテストでパニックになりやすい
- 間違えることに強い不安を感じる
- 「正解じゃなきゃダメ」と思い込んでしまう
🟡 例:「問題を解く前から『できない』と泣いてしまう」
5. 記憶や処理速度に課題がある
- 覚えるのに時間がかかる
- ひとつの問題にすごく時間がかかる
- 繰り返し教えても翌日には忘れてしまう
🟡 例:「九九を何度教えても覚えられない」「テストの制限時間に間に合わない」
6. 教科ごとに得意・不得意が極端
- 算数は好きだけど国語は極端に苦手、またはその逆
- 興味がないとまったく集中できない
🟡 例:「図形問題は得意だけど、文章題になると手が止まる」

発達障害の子どもは、自分で「なにがわからないのか」をうまく言語化できないことも多く、「さぼってる」「ふざけてる」と誤解されやすいのが現状です。しかし実際は、「一生懸命がんばっているのにうまくいかない」苦しさを抱えている子もたくさんいます。
発達障害の子に通信教材がおすすめな理由

発達障害の子どもには、以上のような悩みを抱えていることが珍しくありません。そこでおすすめなのが通信教材です。
通信教材をおすすめする理由は、
1. 視覚支援に強い教材が多い
発達障害のある子どもは、耳で聞くよりも「見て理解する」ことが得意な傾向があります。通信教材は図解・写真・イラストが豊富で、視覚的にわかりやすく作られています。
2. 自分のペースで取り組める
集団が苦手な子でも、自宅ならリラックスして学べます。「今日はここまで」とペースを調整できるので、ストレスが少ないのも魅力です。
3. 習慣化しやすい
毎月教材が届く仕組みは、「やらなきゃ」が「やりたい!」に変わるチャンス。習慣化によって成功体験が積み重なり、自信にもつながります。
発達障害におすすめの通信教材5選

ここからは、特に発達障害の子どもたちに合いやすい通信教材を5つご紹介します。
1. 【すらら】|読み書き・数に困りがある子にも対応
対象年齢:小1〜中3/月額:8,000円前後
読み書き障害(ディスレクシア)や学習障害(LD)への支援として、特別支援学級でも導入されている教材です。アニメーションで「対話形式」で進むレッスンは、発達特性のある子にもやさしい設計。
- ◎ 視覚・聴覚の両方から情報をインプットできる
- ◎ 苦手な単元だけピックアップして学べる
- ◎ 自動音読&繰り返しで記憶定着を支援
👉 おすすめの子ども像:文章を読むのが苦手、授業についていけない子
公式サイト:すらら公式ページ
2. 【RISU算数】|数字に強くなる!視覚支援でわかりやすい
対象年齢:小学生/料金:初月お試しあり+成果連動型
タブレットを使った算数学習に特化。アニメーションと視覚的ヒントで「算数っておもしろい!」という感覚を育ててくれます。実際にADHDやASDのお子さんが使っているレビューも多数。
- ◎ つまずいた問題は「ヒント動画」でフォロー
- ◎ レベルに合った問題が出題されるAI設計
- ◎ ゲーム感覚でモチベーション維持
👉 おすすめの子ども像:集中力が短くてもタブレットなら集中できる子
公式サイト:RISU算数
3. 【天神】|発達段階別にフルカスタマイズ!特別支援版もあり
対象年齢:幼児〜中学生/価格:買い切り型・要見積もり
フルオーダー型の教材で、お子さんの理解度や特性に合わせて内容を個別設計。特別支援版は「発語がない」「指示理解が難しい」などの困難をもつお子さんでも使えるようになっています。
- ◎ 教材内容はすべてプロの発達支援士が監修
- ◎ カスタマイズできるから学年にとらわれない
- ◎ 使い方に関するサポートが手厚い
👉 おすすめの子ども像:既存の教材では合わない・完全個別対応が必要な子
公式サイト:発達障害、グレーゾーンの子の勉強方法に「天神」
4. 【Z会 幼児・小学生コース】|良質な学びと親子の関わり
対象年齢:年少〜小学生/月額:約2,000〜3,500円
「ハイレベルな子の教材」と思われがちですが、実はZ会は「家庭での声かけ」「親子の対話」も重視しており、ASD傾向の子にも向いています。考える力を伸ばす問題が中心です。
- ◎ ワークはシンプル&イラスト中心で負担が少ない
- ◎ 子どもが「なぜ?」を考える機会が増える
- ◎ 親子で取り組めるテーマ型学習が多い
👉 おすすめの子ども像:「会話が苦手だけど興味関心は豊富」なお子さん
公式サイト:Z会の通信教育
5. 【こどもちゃれんじ】発達段階に合わせて選べる
対象年齢:0歳〜年長/月額:約2,000〜4,000円
こどもちゃれんじは、ベビー、ぷち、ぽけっと、ほっぷ、すてっぷ、じゃんぷの6つの年齢別コースが用意されています。
- ◎ 年齢に関わらず発達に応じてコース選択
- ◎ 子どもが興味を示さない場合は退会できる
- ◎ 知育玩具やDVDは療育として活用できる
👉おすすめの子ども像:発達段階に合わせた教材に取り組みたい子
公式サイト:【こどもちゃれんじ】
通信教材を選ぶときのポイント

通信教材とは、発達に凸凹のある子どもたちが「遊びながら学ぶ」ための支援ツールです。
- 年齢と発達段階に合っているか
- 楽しみながら継続できる内容か
- 家庭で使いやすいか(時間・価格・設置場所)
教材を選ぶときは、上記3つのポイントを念頭に置いて選ぶことをおすすめします。
よくある質問(Q&A)

Q1. 通信教材だけで発達支援は十分ですか?
基本的には専門機関での支援と並行して活用するのが理想です。家庭では「補完的な支援」「楽しみながら習慣づける」のが目的です。
Q2. ADHDで集中が続きません。向いている教材は?
短時間でも取り組めるタブレット型教材(RISU算数、すららなど)がおすすめです。
Q3. 費用が気になります。コスパがいいのは?
Z会やRISU、こどもちゃれんじは月額2,000〜3,000円台で始められます。無料体験を利用しましょう。
Q4. 発達に診断がついていなくても使っていい?
もちろんOKです。早期の取り組みが予防にもつながります。
まとめ|通信教材で「できた!」の積み重ねを

発達障害のお子さんは、少しの「できた!」を積み重ねることで、自己肯定感や挑戦する力が育ちます。
通信教材は、そんな「成功体験」の積み重ねを家庭で支援する強力な味方です。
まずは無料で試せる教材や、気軽に始められるドリルなどがおすすめです。
\まずは無料で資料請求から/
【こどもちゃれんじ】