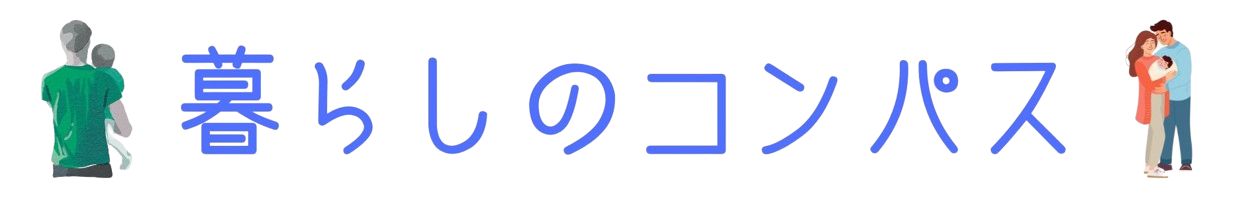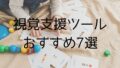こんにちは。社会福祉士のまっさんです。
この連載では、療育の現場で感じる“支援のリアル”を、社会福祉士の視点からお伝えしています。
第6回のテーマは「支援者の迷いと葛藤」。
日々支援に携わる中で、「これでよかったのか?」「本当にこの関わりが正しかったのか?」と自問自答する場面が、何度もあります。
今回は、支援者も“迷っていい”という視点について、実際の現場の声を交えて考えていきます。
療育に「正解」はあるのか?
療育は、医学・心理・教育・福祉といった多領域が交わる支援のかたちです。
それだけに、関わる専門職も、家庭も、そして子ども自身も、「唯一の正解」を見つけにくいのが現実です。
- 「感覚過敏にはこう関わるべき」
- 「こういう行動にはこの支援方法が効果的」
── そんな“教科書通り”にいかないことのほうが、はるかに多い。
子ども一人ひとり、家庭一つひとつに背景と個性があるからこそ、支援に“揺らぎ”はつきものなのです。
支援者が抱える「見えないプレッシャー」
療育や福祉の現場では、支援者自身が次のようなプレッシャーを抱えていることがあります。
● 「ちゃんと成果を出さなければ」
「支援したのに子どもが変わらなかった」と感じると、
「自分の関わりが間違っていたのでは」と自責の念に駆られることがあります。
● 「専門職なのだから、答えを持っているべき」
保護者から信頼を寄せられる一方で、「期待に応えなければ」というプレッシャーがのしかかる場面も。
● 「他の支援者と比べられる不安」
多職種連携の中で、支援方針の違いや評価のずれに戸惑い、「自分だけが間違っているのでは」と感じることも少なくありません。
現場のリアル:「これでよかったのか?」という問い
私が実際に経験した一場面をご紹介します。
ある感情表出が苦手な子に対して、数ヶ月かけて安心感を築き、少しずつ関係性が深まってきた矢先、
「最近、あの子がお部屋に入るのを嫌がってるらしいよ」と他スタッフから耳にしました。
「自分の関わりがプレッシャーになっていたのか…?」
「もっと違う方法があったのでは…?」
一時は深く落ち込みましたが、後日その子がポツリと「でも、〇〇先生がわかってくれるから大丈夫って思ってる」と言ってくれたのです。
“目に見える成果”だけでは測れない信頼関係のかけらが、そこにありました。
「迷い」と「振り返り」は支援者の強み
支援者にとって、迷いや不安は「失敗」ではありません。
それはむしろ、目の前の子どもや家族に真剣に向き合っている証です。
迷いながらも、
- 「今の支援は、この子に合っているか?」
- 「家庭にとって負担になっていないか?」
- 「もっと別のアプローチがあったのでは?」
──と立ち止まり、振り返り、微調整を重ねることこそが、専門職としての“柔らかさ”であり強さなのです。
支援者同士の「対話」と「許し合い」を
迷いを抱えたまま、一人で支援に向き合うことは、とても消耗します。
だからこそ、支援者同士が
- 「こんなケースで悩んだことがある」
- 「私はこう関わってみた」
- 「あのとき、うまくいかなかったけど、また挑戦してるよ」
──そんな言葉を交わせる環境こそが、支援の質を支える“土台”になります。
支援者自身が“安心して迷える場”を持つことは、結果的に支援対象者にも良い循環を生むのです。
保護者へのメッセージ:支援者も“迷いながら向き合っている”
保護者の方へ。
支援者も、実はたくさん悩み、考え、揺れています。
でもそれは、お子さんと、ご家族のことを本気で大切に思っているからこその迷いです。
ですから、もし支援方針に疑問や不安を感じたら、遠慮なく伝えてください。
一緒に考え、寄り添い、修正していけるのが“チーム支援”の本来の姿です。
おわりに|「迷うこと」を肯定する文化を育てたい
「迷いがあるからこそ、成長がある」
「正解がないからこそ、その子に合った支援を探し続けられる」
療育の現場において、支援者自身が自分の迷いを否定せず、他者と分かち合える文化が広がっていくことを願っています。
そしてそれは、支援の質を高めるだけでなく、
子どもたちにも、「大人も迷っていい」「完璧じゃなくていい」という大切なメッセージになるはずです。
次回は、「【第7回】現場で感じた“違和感”を大事にする|制度と現実のすき間で生まれるもの」
制度やマニュアル通りにはいかない現場で感じる「モヤモヤ」こそ、支援を見直す大切なヒントであることについてお伝えします。
関連記事はこちら
⇒第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
⇒第5回 兄弟児が抱える“見えない葛藤”|親が気づきにくいサインとは?