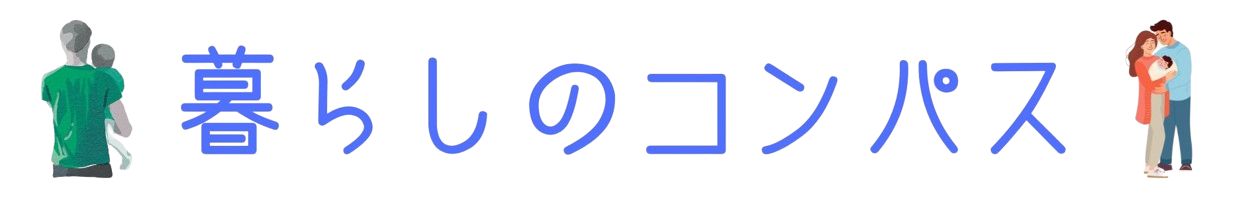「服は毎日同じじゃないとイヤ」「お皿の色が違うだけで大泣き」
――そんなこだわりの強い子どもへの対応に悩んでいませんか?
本記事では、障害福祉の現場で10年以上の経験を持つ社会福祉士・精神保健福祉士の筆者が、
こだわりへの対応に困っている保護者や支援者向けに、安心して実践できる3ステップを解説します。
こだわりが強い子どもの背景と特性

こだわりの強い子どもたちは、しばしば以下のような傾向を持っています。
- 感覚が過敏で、小さな変化にも敏感に反応する
- 急な変更や予測できない出来事が苦手
- 一度決めたルールや順番を大切にする
こうした傾向は、発達特性によるものが多く、「わがまま」や「甘え」ではありません。
安心を得るための“自己調整の方法”として、こだわり行動が現れている場合もあります。
こだわりが強い子どもへの対応3ステップ

ステップ1:「誰が困っているか?」を見極める
まず最初に立ち止まりたいのが、「そのこだわりで本当に困っているのは誰か?」という視点です。
- 子ども自身がパニックを起こしているならサポートが必要
- 親の都合やスケジュールが問題なら、大人側の工夫も必要
すべてのこだわりに介入しなくていい。命や安全に関わらない限り、スルーできることもあります。
ステップ2:「やめさせる」より「選択肢を広げる」
こだわりを強制的にやめさせようとすると、かえって不安や反発が強まります。
そこでおすすめなのが「幅を広げる」というアプローチ。
例えば、
「毎日赤いTシャツじゃないとダメ」
→「今日は赤が入ったTシャツならどうかな?」
→「赤と青がある服も大丈夫かも?」
少しずつ“安心のゾーン”を広げるイメージで、選択肢を提案していくことが大切です。
ステップ3:「予告・見通し・選択肢」の安心セット
こだわりの強い子どもは、「このあと何が起こるか分からない」ことに強い不安を感じています。
そこで有効なのが、以下の3つをセットで伝える方法です。
| 安心の要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 予告 | これから何をするか伝える | 「あと5分でお片付けするよ」 |
| 見通し | 流れや順番を説明する | 「片付けたらおやつの時間だよ」 |
| 選択肢 | 小さな選択肢で自己決定を促す | 「おもちゃ箱に入れる?それともブロックから片付ける?」 |
安心できる情報が事前にあれば、見通しが持てて落ち着きやすくなります。
よくあるQ&A

Q. どうしても外せないこだわりがあるときは?
A. “それを守ることで安定して過ごせる”なら、あえて守らせることも大切です。
無理に取り上げるより、他の方法で生活の幅を広げましょう。
Q. 周りの人に理解してもらえません…
A. こだわり行動は一見「甘え」や「わがまま」に見えることも。
その背景や理由を保護者が説明できると、周囲の理解が得やすくなります。
▶ 例:「この行動は安心するためのルーティンなんです」など
まとめ|こだわり=その子の安心感
こだわりの背景には、「これがないと不安」「順番通りじゃないと混乱する」といった気持ちが隠れています。
- 誰が困っているかを見極め
- やめさせずに幅を広げ
- 見通しと選択肢で安心を届ける
この3ステップを大切にすることで、こだわりの強い子への関わり方・向き合い方がラクに、そして前向きになります。