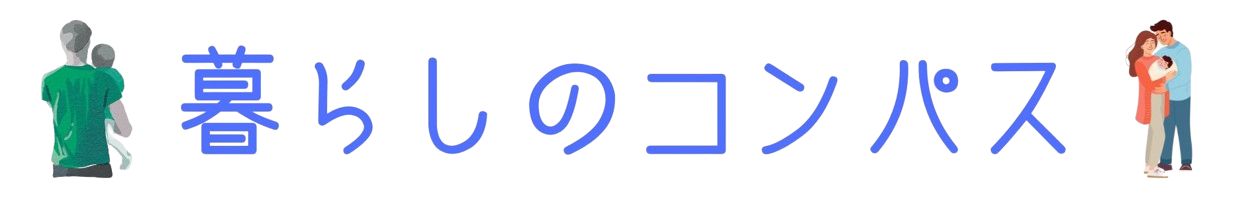療育を始めたばかり、または通い慣れたはずの時期に「行きたくない」「やだ!」と子どもが泣き出すことがあります。
そんな時、親としては――
- 「せっかく申し込んだのに…」
- 「行かないと発達が遅れるのでは?」
- 「無理にでも通わせるべき?」
と焦りや不安を抱きがちです。
私はこれまで10年以上障害福祉に関わり、多くの子どもたちと関わってきました。その中で、“嫌がる子”ほど大切にしたいサインがあることに気づかされています。
この記事では、
- 子どもが療育を嫌がる理由
- 無理に通わせるべきかどうか
- 教室長として実践している具体的な対応法
- 親ができる5つの工夫
をお伝えします。
子どもが「療育を嫌がる」よくある理由とは?
子どもが療育を嫌がる背景には、いくつかの共通パターンがあります。
① 環境の変化が苦手(見通しが立たない)
発達が気になる子どもたちは、「初めての場所」「先が読めないこと」に強い不安を感じやすい傾向があります。
たとえば、
- 毎回スタッフが違う
- 活動内容が急に変わる
- 教室までの流れが定まっていない
など、「見通しのなさ」が拒否感につながることがあります。
② できない体験が続いている
療育はあくまで「楽しく学ぶ場所」ですが、子どもにとっては「うまくできなかった」「注意された」と感じてしまう場面もあります。
自尊感情が下がることで、「もう行きたくない」という気持ちに。
③ 疲れすぎている・他の予定と重なっている
幼稚園や保育園のあと、疲れているタイミングでの療育は、心身ともに余裕がない状態です。遊びや習い事と時間がぶつかると、「どっちも頑張れない」状況にもなります。
④ 保護者の不安・焦りが伝わっている
子どもは親の気持ちに敏感です。親が「しっかりやってね」「落ち着いて先生の話を聞いて!」と緊張していると、それがプレッシャーになって拒否反応を引き起こすことも。
無理に通わせるべき?プロの視点からの答え
【結論】無理に通わせる必要はありません。
ただし、“行きたくない気持ち”と“支援の必要性”は分けて考えることが大切です。
無理に通わせた結果、逆効果になることも…
- 療育そのものが「嫌な場所」になってしまう
- 対人不信や自己肯定感の低下を招く
- 家庭での関係性がギクシャクする
これでは本末転倒です。通い続けることよりも、「通いやすく整えること」が優先されるべきです。
教室長が実践している「療育を嫌がる子」への対応法
私が現場で行っている対応の一部をご紹介します。
① 事前の「予告」と「スケジュール可視化」
- 絵カードや写真で「今日はこの先生と、こんな活動だよ」と伝える
- ホワイトボードで活動の流れを見える化
→ 安心感が生まれ、拒否が和らぐことがあります。
② 無理に引き離さず、親子一緒に活動
- 最初の10分だけ同席してもらう
- 「親子療育」の形式でスタート
→ 安心基地としての存在が、子どもの挑戦を支えます。
③ 成功体験を重ねるプログラムへ調整
- 「できた!」と感じやすい活動に変える
- 小さなステップに分けて、達成感を演出
→ “また来たい”と思えるきっかけに。
親ができる5つの関わり方
家庭でのサポートも、療育継続の鍵になります。
① 子どもの「できた」を拾って言葉にする
→「先生にこんにちは言えたね!」「電車のおもちゃ、上手に貸してあげてたね」
② 療育前後に“安心するルーティン”をつくる
→ おやつ・お気に入りのおもちゃ・絵本など
③ 担任・療育者と連携し「気になる様子」を共有
→ 無理なく調整してもらえることも多いです
④ 一時的なお休みを視野に入れる
→ 状況が落ち着いたら再開、でもOK。休むこと=後退ではありません
⑤ 親自身も「完璧じゃなくていい」と認める
→ 親が自分を責めすぎると、子どもも緊張します。「大丈夫、一緒にがんばろうね」でOK。
5. まとめ:嫌がる気持ちは、成長のサインでもある
子どもが「療育に行きたくない」と言うのは、感情や状況を言葉で表現できている証拠でもあります。
無理に通わせるのではなく、
- 「なぜ嫌なのか?」
- 「どうしたら安心できるか?」
を一緒に考えることで、子どもはまた一歩前に進めます。
そして、親自身も“頑張りすぎない”ことが、長く支援を続けるポイントです。