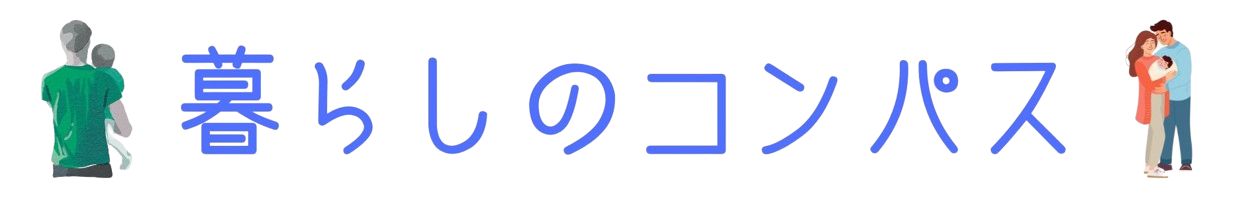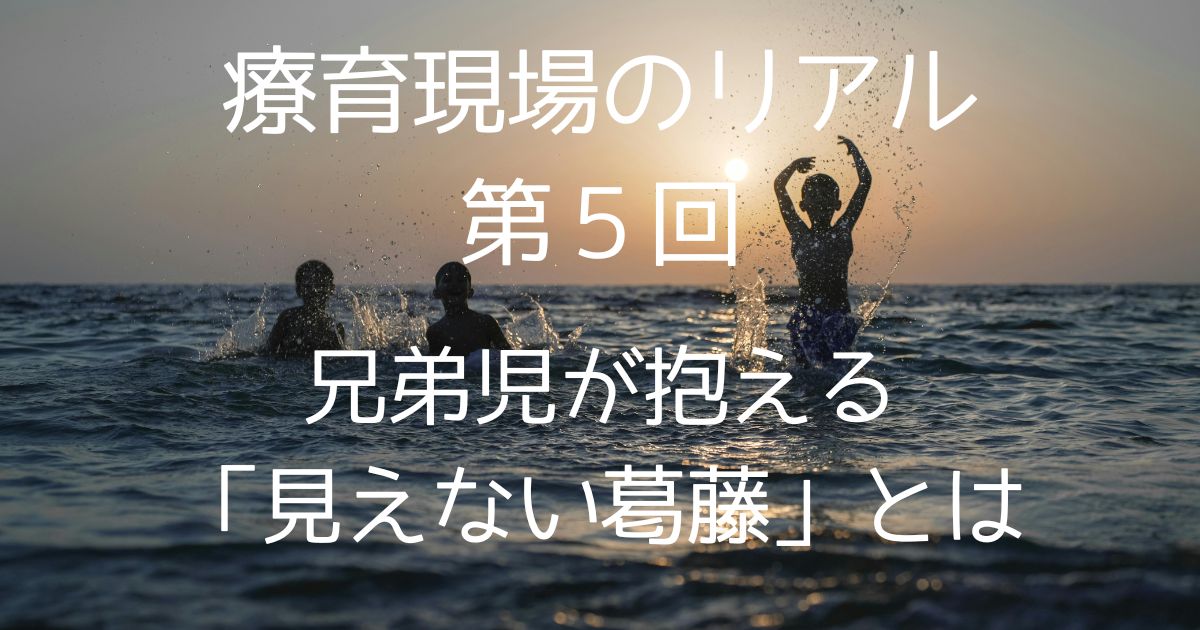こんにちは。社会福祉士のまっさんです。
本連載では、療育現場で出会う“家族の声”をもとに、支援の視点を深掘りしています。
第5回のテーマは、「兄弟児(きょうだいじ)」──発達に特性のある子どもの兄弟姉妹が、どんな葛藤を抱えているのか、そしてそれに大人がどう気づけるか、を社会福祉士の立場からお伝えします。
兄弟児とは?注目されにくい“もう一人の子ども”
「兄弟児(きょうだいじ)」という言葉を知っていますか?
発達障害や重度障害など、特別な支援が必要なきょうだいを持つ子どものことを指します。
支援の現場では、どうしても「支援が必要な子」に焦点が当たりがちです。
でも、その陰で“がんばっているもう一人の子ども”がいることを、私たちは忘れてはいけません。
なぜ兄弟児は「気づかれにくい」のか?
兄弟児の支援が見落とされやすい理由は、主に以下の3つです。
1. 「しっかりしてる子」に見える
周囲の大人にとって、兄弟児は“手がかからない”“おとなしい”印象を持たれることが多く、「大丈夫な子」と認識されてしまうことがあります。
2. 「お兄ちゃんなんだから」「お姉ちゃんなんだから」と我慢させられる
年齢や立場的に、「がまんする役割」を無意識に背負わされていることもあります。
3. 親が気づきにくい
特性のある子のケアに追われ、他の子どもの心のサインに目が向きにくいというのは、どの家庭でも起こりうることです。
兄弟児が抱える“見えない葛藤”とは?
支援現場で聞こえてくる兄弟児の声には、さまざまな感情が複雑に絡み合っています。
● 「もっと自分も見てほしい」
「いつもお兄ちゃんのことで忙しそう」
「一緒に遊んでほしいけど、言えない」
● 「いい子にしてなきゃ」
「私までわがまま言ったら、ママ困る」
「泣いたら怒られるかも…」
● 「なんであの子ばっかり?」
「なんでお兄ちゃんだけ特別なの?」
「ずるいって思っちゃいけないのかな」
● 「自分のせいかもしれない」
「私がもっとちゃんとしてたら…」
「お兄ちゃんのこと、嫌だと思ったからバチが当たったのかな」
こうした感情を、子ども自身がうまく言語化できないまま心に溜め込んでいるケースも多く見られます。
親が気づきにくいサインとは?
兄弟児は、自分の感情を抑えたり、表に出すのを遠慮したりする傾向があります。以下のようなサインは、支援者から見て「気づいてほしいSOS」の可能性があります。
行動の変化
- 以前より甘えが強くなった
- 急に反抗的な態度を取るようになった
- 不安や緊張が強まり、チックや体調不良が出る
感情のコントロールが難しくなる
- 些細なことで泣く・怒る
- 「どうせ自分なんて…」と自己否定的な言葉を使う
学校や保育園・幼稚園での不調
- 集中できない
- 友達関係が不安定になる
- 登園・登校を嫌がる
「この子、最近変わったな」と感じたら、背景に“家庭での葛藤”が潜んでいることも考えられます。
兄弟児も支援の対象に
支援者として、また保護者として、兄弟児をどう支えていけばよいのでしょうか?
● 1対1での時間を意識的に作る
ほんの10分でも、その子だけと向き合う時間があることで、子どもの安心感が大きく変わります。
● 感情を安心して話せる場をつくる
「そんなふうに思ってもいいんだよ」
「正直に話してくれてありがとう」
子どもが抱くネガティブな感情に対して、「そんなこと思っちゃだめ!」ではなく、受け止めてあげることが第一歩です。
● 園・学校や支援機関との連携も視野に
担任の先生やスクールカウンセラーと情報を共有することで、兄弟児の見守り体制を広げることができます。
保護者も、自分を責めないで
「兄弟児にしわ寄せがいってしまっているのでは」と、保護者の方が罪悪感を抱くケースもあります。
でも大切なのは、完璧を目指すことではなく、「今、気づけたこと」が大きな一歩だということ。
支援者としても、保護者を責めることなく、家庭全体が少しずつ楽になっていける道を一緒に探していく姿勢が大切です。
最後に|兄弟児にも「安心できる居場所」を
発達障害のある子どもに対する支援が進む中で、
その兄弟姉妹が「見えない我慢」を抱えていないか。
その子の笑顔は「本心」なのか、「役割」なのか。
家族全体を見る視点を忘れずに、兄弟児の気持ちにも光を当てていきたいと思っています。
次回は、「【第6回】支援者も迷っていい|「正解がない」療育の現場から見えてきたこと」
支援者が抱える葛藤や限界をテーマに、専門職のリアルと、自分自身のケアの重要性についてお伝えします。
関連記事はこちら
⇒第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
⇒第4回 “普通でいてほしい”気持ちと向き合う|家族の期待と現実のあいだで