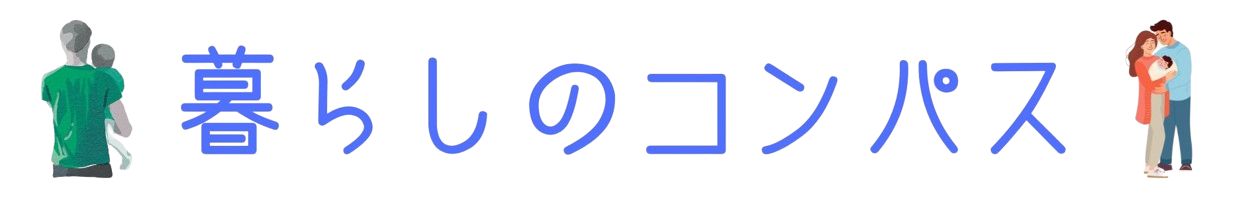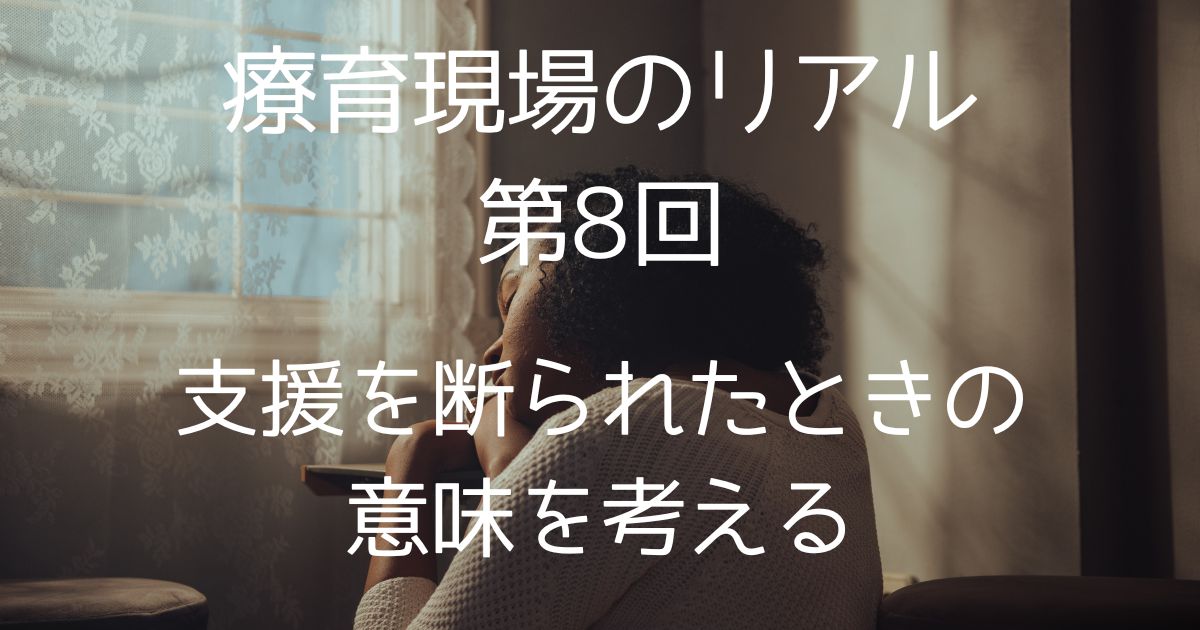こんにちは、社会福祉士のまっさんです。
この連載では、療育の現場で実際に感じたことや、支援者として大切にしている視点をお届けしています。
今回のテーマは、「支援を断られたとき」に感じる“壁”の正体について。
支援者として提案した内容が拒否されたり、保護者から距離を置かれたりする経験は、少なからず誰もが通る道ではないでしょうか。
でもその背景には、保護者の“否定的な感情”だけではない、深い理由や想いが潜んでいることが多いのです。
「断られる=敵意」ではない
支援の現場では、「この子にはこの支援が有効だ」と思える提案をしたとしても、
保護者から「いえ、大丈夫です」「今は結構です」と断られることがあります。
支援者の側からすると、
- 「せっかく子どものためを思って提案したのに…」
- 「受けてもらえたら、もっと楽になるはずなのに」
- 「なぜ拒否されるのか、理解できない」
といったモヤモヤを感じるかもしれません。
でも、“断る”という行動には、それを選ばざるを得ない背景があるのです。
「支援不信」の根底にあるもの
保護者が支援を拒否するとき、そこには以下のような要因が隠れていることがあります。
1. 過去に傷ついた経験
「支援を受けたけど、結局何も変わらなかった」
「支援者に否定された」「理解してもらえなかった」
そんな体験があると、「また同じことになるのでは」と防衛的になるのは自然なことです。
2. “頑張りすぎている”サイン
支援を断る保護者ほど、実は日々の育児や支援を一人で背負いすぎていることがあります。
「自分でやるしかない」「これ以上人に頼れない」──それは孤独の裏返しでもあります。
3. “支援=できていない証”という誤解
一部の保護者にとって、「支援を受けること」は、「親として至らない」とレッテルを貼られるように感じてしまう場合もあります。
「不信」ではなく「信じたいからこそ拒む」こともある
あるお母さんが、最初の面談で私にこう言いました。
「もう期待したくないんです。前にも“ちゃんと話を聞く”って言われたけど、結局、書類通りの支援しかしなくて…」
その後、何度か雑談ベースのやり取りを重ねて、ようやく彼女の口から出た言葉が、
「ほんとは…誰かにわかってほしかっただけなのかもしれないです」
拒否の裏には、“期待”や“願い”が押し込められている。
信じたかったけど、裏切られたくないからこそ、心のシャッターを閉める。
そんな人の心の構造を、支援者は理解しておく必要があります。
断られたとき、支援者ができること
1. 否定的に受け取らない
「断られた=拒絶された」と感じると、支援者自身も傷つき、関係が途切れてしまいます。
でも、一歩引いて相手の背景を想像する視点があると、次のアプローチにつながります。
2. “関わり続ける意思”を伝える
たとえばこんな言葉が有効です。
「またタイミングが合ったら、いつでも声をかけてくださいね」
「今は必要ないかもしれませんが、何かあれば私たちはここにいます」
このように、“あなたのペースでいい”というメッセージを示すことが、信頼を育てる第一歩です。
3. 支援の選択肢を“減らさない”
支援の提案を断られても、代わりになる選択肢を持ち続けることが大切です。
本人や家庭の変化に合わせて「今ならこれが合うかも」と再提示する機会を作りましょう。
保護者へのメッセージ:「断ること」は悪いことではありません
支援を「断る」ことに罪悪感を持つ必要はありません。
支援とは、“自分が必要だと感じたときに、手を伸ばせる”ものであっていいのです。
でも、もし心のどこかに「誰かに話を聞いてほしい」「助けてほしいけど迷っている」気持ちがあるなら──
その小さな声を、どうか大事にしてみてください。
支援者は、いつでもあなたのそばにいる準備をしています。
まとめ|支援は「タイミングと関係性」
支援の成否は、提案の内容だけで決まりません。
その人との関係性、そして“今このタイミング”で何が必要かを感じとる力が、支援者には求められます。
断られたときこそ、相手の「今は違う」という声を尊重する。
その姿勢が、信頼の土壌を育て、将来の支援につながっていくのです。
次回は、「【第9回】“正しさ”が人を傷つけるとき|支援者に必要な「共感力」とは?」──良かれと思った言葉が相手を追い詰めてしまう──。支援者として「正しい支援」と「伝わる支援」の違いに向き合います。
関連記事はこちら
▶第1回 療育は子ども支援だけじゃない。家族まるごと支える社会福祉士の視点
▶第7回 現場で感じた“違和感”を大事にする|制度と現実のすき間で生まれるもの