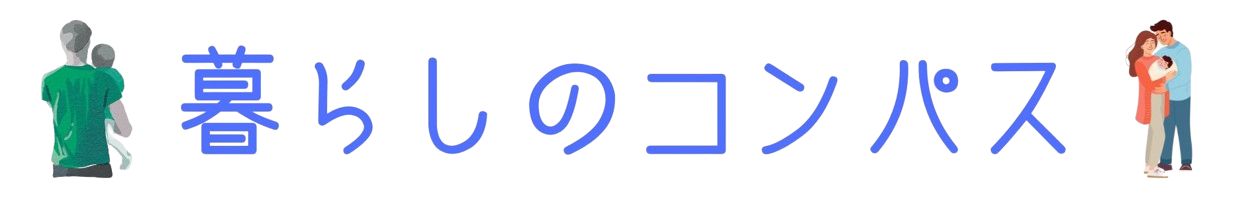「私のことも見てほしいけど、我慢しなきゃいけない…」
「お兄ちゃんが泣いてると、ママは私の話を聞いてくれない」
そんな“声にならない声”を心の中に抱えている子どもたちがいます。
それが、「きょうだい児」と呼ばれる存在。
障害や特別な支援を必要とする兄弟姉妹がいる子どもたちのことを、福祉の世界ではそう呼びます。
この記事では、きょうだい児が抱えやすい悩みや気持ちに寄り添い、今日から家庭でできる10の支援・工夫をご紹介します。
きょうだい児とは?
きょうだい児とは、障害や慢性疾患、発達に特性のある兄弟姉妹を持つ子どものことです。
見た目には「元気で大丈夫そう」でも、心の中にはさまざまな思いを抱えています。
きょうだい児が抱えやすい5つの悩み

① 注目されにくい・愛されていないと感じる
- 親がきょうだいのケアにかかりきりで、自分にはあまり目が向かないと感じてしまう。
- 「いい子でいなきゃ」と思い、自分の気持ちを言えなくなる。
② 感情を我慢しやすい
- 怒りや不満、寂しさを言葉にせず、内に抱えがち。
- 「うるさくしちゃいけない」「泣いちゃダメ」と無意識に我慢する。
③ 周囲との違和感・孤独感
- 「うちだけ何か違う」と感じることがある。
- 友達に家庭のことを話せず、理解者が少ない。
④ 兄弟姉妹の行動に対する恥ずかしさや困惑
- 公共の場で兄弟姉妹が大声を出したり、パニックになったりすると、どう振る舞えばいいかわからず戸惑う。
- 周囲の視線や偏見を感じやすい。
⑤ 将来への不安
- 「大人になったら私が面倒を見るのかな?」と、年齢に不相応な不安を抱えることも。
きょうだい児が抱える思いの背景にあるもの

● 家族の構造的な「やさしい不平等」
- 障害のあるきょうだいへの手厚いケアがある一方、健常児であるきょうだい児は「大丈夫」とされやすく、結果的に支援の網からこぼれやすい。
●「がんばり屋さん」になりやすい傾向
- 親を困らせたくない、助けになりたいという思いから、早く大人びたり、自分の気持ちを抑え込む子も多い。
きょうだい児の心に寄り添う10の方法

1. 話す時間を「意識して」つくる
障害のあるお子さんの対応で忙しい毎日でも、きょうだい児との“1対1”の時間を意識してつくることが大切です。たとえ5分でも「今日はどうだった?」と丁寧に関わることで、「自分も大事にされている」と感じることができます。
2. 障害や支援のことを“子どもにもわかる言葉”で説明する
きょうだい児は、家庭で起きていることに対して疑問や不安を持っています。難しい言葉ではなく、子どもの年齢に合った言葉で「どうして特別なサポートが必要なのか」を説明すると、納得しやすくなります。
3. がんばりや思いやりに「言葉で」感謝を伝える
きょうだい児が我慢したり、協力してくれたときには、「ありがとう」と言葉で伝えることが大切です。「助かったよ」「おかげで〇〇できたよ」と具体的に伝えることで、きょうだい児の存在が認められたと感じることができます。
4. きょうだい児が主役になれる場面を用意する
日常の中で「きょうだい児だけが主役になれる時間」も必要です。習い事の発表会、誕生日のお祝い、学校行事など、「今日はあなたが主役だよ」という場面があると、自己肯定感が育まれます。
5. 一緒に遊ぶ時間を短時間でもとる
忙しい日々の中でも、親子で遊ぶ時間は子どもにとっての“心の栄養”。お風呂の中でクイズ遊びをしたり、寝る前に一緒に絵本を読むだけでも「親とつながっている」と感じることができます。
6. 感情表現を受け止め、否定しない
きょうだい児が怒ったり泣いたりすることは「当然」の感情です。「我慢しなさい」「わがまま言わないの」と否定せず、「そう思ったんだね」「そういうときもあるよ」と受け止めることで、感情を安心して出せる関係が築けます。
7. きょうだい児が抱えている役割を軽くする工夫をする
「いい子」「しっかり者」と期待されることが多いきょうだい児。家の中での“お兄ちゃん役”や“手助け役”を少しでも軽くしてあげる工夫が必要です。「今日はママがやるからゆっくりしててね」など、安心して子どもらしくいられる環境を作りましょう。
8. きょうだいそれぞれに合わせた“ごほうび”を取り入れる
支援グッズや視覚支援ツールのように、「がんばり表」「シール台帳」などを活用して、きょうだい児にも達成感や楽しみを感じられる仕組みをつくるのも有効です。
9. 他のきょうだい児とのつながりをつくる(きょうだい児の会など)
同じ立場のきょうだい同士が集まる「きょうだい児の会」や、専門職が行うグループ支援に参加することで、「自分だけじゃない」と思えることも。インターネット上のコミュニティなども活用できます。
10. 保護者自身が「自分を責めない」ことも大切
きょうだい児への対応に悩む保護者は多いもの。でも「ちゃんと向き合おう」と思った今この瞬間が、支援のスタートです。完璧を目指さず、少しずつできることを増やしていきましょう。
大人ができる3つのこと

1. 「見えていない気持ち」に目を向ける
発言しないからといって、感じていないわけではありません。沈黙の中にある気持ちを想像する視点が大切です。
2. 親も自分を責めない
「もっとしてあげたいのに…」という気持ちはとても自然なもの。完璧な支援は難しくても、少しずつ“気づき”を持てるだけで大きな変化になります。
3. 「話せる場」をつくる
学校や支援者、親戚などにきょうだい児の背景を共有することで、日常の中でも話せる・頼れる大人が増えます。
よくあるQ&A|支援者・保護者の悩みに答えます

Q1:うちの子は何も言わないけど、大丈夫?
→ 表に出さないだけで、心の中でいろんなことを感じていることが多いです。「大丈夫?」と聞くのではなく、「最近〇〇で頑張ってるね」と声をかけることで気持ちを引き出しやすくなります。
Q2:きょうだい児に障害についてどこまで話せばいい?
→ 年齢や発達段階に応じて伝えましょう。「どうして〇〇くんだけ支援学級に行くの?」と聞かれたら、「〇〇くんはお話がゆっくりだから、わかりやすい授業を受けてるんだよ」と説明するなど。
Q3:きょうだい児の気持ちを育てる絵本や教材ってある?
→ 絵本『わたしの弟、特別なんだ』『がんばりやさんのきょうだい』などはおすすめです。絵本の世界を通して、自分の思いに気づくきっかけにもなります。
まとめ|“あなたの気持ちも大事だよ”を伝え続けよう
きょうだい児は、家庭の中で見えない思いを抱えていることがあります。しかし、保護者や周囲の大人が「あなたも大切な存在だよ」と伝えるだけで、子どもたちの安心感は大きく変わります。
「きょうだい児支援」は特別なことではなく、日常の中のちょっとした“気づき”と“声かけ”から始まります。今日できることから、一歩ずつ取り入れてみてくださいね。