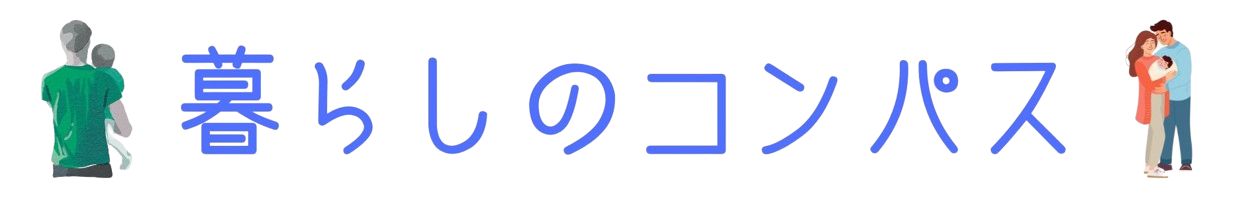発達支援や療育に通うお子さんがいるご家庭で、
「兄弟姉妹のケアまで手が回らない」という悩みは非常によく聞かれます。
- 我慢させてばかりで申し訳ない
- 本当はもっと構ってあげたいのに
- 「いい子」でいてくれるけど心の中が心配
きょうだい児は、「手がかからない分、後回しにされがち」なのが現実。
けれどそのまま放っておくと、寂しさ・怒り・自己否定感といった感情が長く尾を引いてしまうこともあります。
この記事では、きょうだい児が抱える“見えにくい心の傷”、すぐにできる10の支援ヒント、家庭での実践例と声かけのコツをわかりやすく解説します。
「きょうだい児」とは?療育家庭における位置づけ

きょうだい児とは、障害や発達に課題のある子の兄弟姉妹のことを指します。
特に療育に通うお子さんの兄弟姉妹は…
- 日々の送迎に付き添う
- 親の目が届きにくい
- 遊びや予定を我慢することが多い
- 学校や友だちに話しづらい
…という背景から、子どもながらに気を使い、自分の気持ちを抑え込んでしまうことがあります。
なぜ「きょうだい支援」が必要なのか?

問題が“見えにくい”からこそ注意
きょうだい児は「困っているように見えない」ことが多く、支援の優先度が下がりがちです。
けれど本音はこうかもしれません。
「私のことも見てほしい」
「どうして弟ばかり特別なの?」
「頑張っても親に褒めてもらえない」
これらは後に自己肯定感の低下や反抗行動として現れることもあります。
【家庭でできる】きょうだい支援10のヒント

① 名前を呼んで「あなたに関心があるよ」と伝える
小さな声かけが、「見てもらえている」という安心感につながります。
② 毎日1分でも「きょうだいだけの時間」を作る
1対1の関わりは、たとえ短時間でも心に残ります。
③ 小さな努力や我慢を言葉で認める
「ありがとう」「助かったよ」と“行動”に光を当てましょう。
④ 感情を引き出す声かけを意識する
「寂しかった?」「つまんなかった?」と、感情に名前をつける習慣を。
⑤ 「我慢させてごめんね」より「ありがとう」に変える
謝罪より感謝の言葉が、自己価値を育てます。
⑥ 特別なイベントを用意する(兄弟児DAYなど)
たとえば月1回だけ「兄だけのお出かけ」など、“優先される経験”を意図的に。
⑦ お手伝いは「やってくれて嬉しい」と伝える
戦力ではなく、関係性の一部としての“関わり”を。
⑧ 保育園・学校の先生とも連携を
きょうだい児の心の変化に気づく外部の目はとても重要です。
⑨ 家族の「気持ちを話す場」をつくる
家庭内で“気持ちの話をしていい雰囲気”を意識しましょう。
⑩ 必要に応じて外部支援も検討する
児童相談所、ファミリーサポート、カウンセリングなど、頼れる場所はたくさんあります。
【実例】療育現場でのきょうだい支援エピソード

「弟が療育に通っていて、どうしても妹を待たせることが多い。
でも、帰り道に“ママは今日、〇〇ちゃんの顔が一番かわいかったな~”って言うようにしたら、
妹がニッコリ笑うようになったんです。」
日常の中にある小さな配慮と声かけこそ、きょうだい支援の原点です。
よくある質問(Q&A)
Q1:兄弟げんかが多いのですが、どうすればいい?
A:兄弟げんかは“親にかまってほしい”サインの可能性も。
まずは1対1の時間を増やし、冷静な時に気持ちを聞きましょう。
Q2:親が疲れて支援どころじゃない…
A:親が無理をすると、支援は長続きしません。
まずは「できることから・完璧じゃなくていい」と捉え直しましょう。
※おすすめ記事:
➡【本音で語る】きょうだい児支援に疲れたら|がんばりすぎないための7つの視点
まとめ|きょうだいの心に寄り添うことも、療育の一部です
きょうだい児支援は、「特別な支援者でなくても」始められます。
家庭の中で、日々の関わりの中で、小さな“心の充電”をしていくこと。
それが結果的に、家族全体の安心感と、きょうだい関係の良好な土台につながります。
焦らず、できることから。
今日から一つ、小さな一歩を踏み出してみませんか?